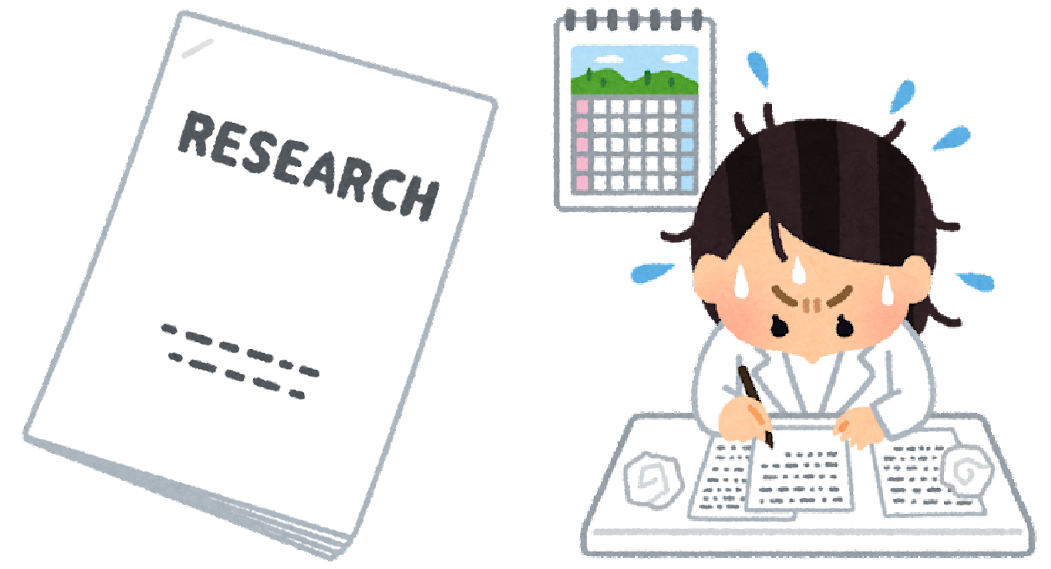概要
ジャーナルから依頼された査読についての日記です。
経過
2023-7-10:International Journal of Environmental Research and Public Health (IJERPH)というジャーナルから依頼された査読。このジャーナルは、Sciamago Journal & Country Rank (SJR)のPublic HealthのジャンルでQ2にランクされているので、それなりのジャーナルのよう。お題はアキレス腱(非付着部)症のレビュー。期限が1週間しかなく、7月12日とせまっている。イタリアの大学からの論文で、二人で原稿を準備したのち、複数人で編集・査読、さらに複数の監督者がチェックののち、全員が投稿原稿に同意したという気の入れよう。大学から複数人の共著者で論文を出すのなら、このくらいしてほしいものだ。おかげでこちらから指摘することはほとんどない。
2023-7-11:それにしてもずいぶんしっかりとしたレビューだと思ったので、共著者を調べたら、Maffulli先生と関係のあるグループらしい。責任者はMaffulli先生のところで論文を10本書いているし、筆頭著者もこれが6本目の論文のよう。アキレス腱症(アキレス腱付着部症・非付着部症)のうち、アキレス腱非付着部症にだけ限定したレビューであることがあいまいだったので、そこだけ指摘して提出。こういう査読は楽だ。
などと思っていたら、IJERPHの副編集長からメール。レビューを送ってくれてありがとうと言いつつも、以下の質問に答えて下さいと、レビューの追加を要求された。あまりにあっさりしすぎたか。とりあえず回答して返送。ついでにレビューアーのサイトを見ると、もうひとりの査読者のコメントを見ることができた。すると、かなり手厳しい評価(各評価項目5段階で2や3ばかり)。しかしよくよく査読コメント見ると、確かにそう直してもよいが、別に今のままでも大差はない、というものばかり。査読者は自分でレビューを書いたことがあるのだろうか。これだけの文献を参照しながらレビューを書くというのは大変なんですよ。それなら、自分が文献を読む手間を省かせてくれて、これだけの文献をまぁまとまりよく提示してくれるレビューをありがたいと思わないのだろうか。こういう、人にばかり厳しいタイプには、「じゃあお前の論文見せろよ」と言いたくなる。
2023-7-12:続いて、Foot & Ankle Specialistから依頼されている靴に関するレビュー論文の査読。締め切りが7月19日。
2023-7-13:FASの論文の査読。査読は締め切り間際にやるよりも、毎日少しずつ読み進めてはコメントを書いていく方がよいと思ってきた。結局最初に思いついたことが有効な意見なことが多い。
2023-7-15:FASの論文の査読。興味のないレビュー論文は苦痛だということがよくわかった。
2023-7-19:FASの論文の査読。2度目に読んだら1度目ほど苦痛ではなかった。レビューゆえ記述のほとんどは文献の引用なので、ほとんど直すところがない。厚底ランニングシューズについてのレビュー論文なのに「人類の歩行は…」といった大上段に構えた書き出しをしていたので、そういう冗長な記述は不要だと指摘。あとはマイナーリビジョンをいくつか指摘して終了。提出。
2023-7-23:2023-6-11に提出したFASの査読に対し、論文が修正されたので再度査読してくださいとの依頼が先週来ていたので、その査読。だいぶましになっている。ここでまぁいいやとしてしまうか、しつこく修正点を指摘するか、迷うところ。
2023-7-26:やはりしつこく指摘することに。もう一度最初から読み直して、気になるところを指摘。期限は現地時間の8月1日まで。足の外科では有名なTH Rui先生のグループからの論文だからか、初回はずいぶん甘く査読してしまったようで、よくよく見れば書き方はかなりお粗末だ。とくに気になるのは、方法と結果が一致していない点。何をやって、その結果がどうだったのかは、ちゃんと対応させて書かなければならない。
2023-7-27:昨日の続きのFASの論文の査読。どうしてこう図の説明が雑なのだろう。説明が雑で非をとがめられるのは著者自身なのに。
2023-7-28:昨日の査読の続き。ほぼ完成。
2023-7-30:査読コメントを見直した上で提出。書き方は稚拙な個所も多いが、論文のネタとしては十分にアクセプトされてよいものなので、こちらはひたすらに添削者にならざるを得ない。
2023-8-17:FASから、7/30に提出した査読に対する修正が著者から提出されたのでまた査読してください、とメールが来た。途中で投げ出すわけにもいかないので承諾。早速見ると、アブストラクトは言われるがままに直しているが、その結果、制限語数の250語をオーバーしている(269語)。どうしてこういうことになってしまうのだろうのか。どんな訂正をするのであれ、投稿規定を守るのは当たり前だろう。「Abstractを訂正する際は、制限語数をはみ出さないように注意して下さい」と言わなければならないのか(バカなのか)。他には、図に関して、前のときに図のタイトルと図の説明を一緒にしたような記述になっているから、「図のタイトルと図の説明をわけて書いてください」と書いたら、図のタイトルは「図1」だけになっていて、残りの記述をすべて「図の説明」としていた。図のタイトルが「図1」って。。これに関しても、他の論文を見て、図のタイトルとか説明をどのようにすればいいのか参考にしよう、とか思わないのか。というかそもそも上級医師にちゃんと見てもらってから提出したのか(TH Lui先生にちゃんと見てもらったのか)。こういうふざけた訂正の仕方を見ると、1回Rejectを食らって出直した方がいいのではないかと思ってしまう。こういう論文にどこまで付き合うか。
2023-9-4:あまりに書き方が稚拙すぎるため、査読に嫌気がさして放っておいた論文の査読の締め切りが今日。もうやらざるを得ない。投稿規定の図の説明の部分を見ると、ほとんど指示がないので、この稚拙な図の説明も投稿規定違反とは言えない。まぁ意味が通らなくもないので、そのまま放置。図の中の記号も小さすぎるが、これも投稿規定には記載がないし、何ならアクセプト後に出版社から指摘があるだろう。こんなところに構っていられない。アブストラクトは投稿規定によれば200語だった!なんと69語もオーバー。これは看過できないので修正するよう指摘。ディスカッションの書き方も言ったらきりがない。イントロダクションで、科学の広い海の中から未解決の特定のテーマを絞り込み、それに対して研究、出てきた結果を一般化可能性の観点から議論し、科学に還元する、という作業をやっている以上、必然的にイントロダクションとディスカッションは逆構造になるべきだが、このディスカッションは、多くのダメなディスカッションと同様、いきなり過去の文献について述べはじめ、「それらの文献と自分たちの論文結果は一致していました」という、他に迎合するような論調となっている。他と食い違わなくてほっとするようなお友達感覚の人は論文なんて書くなよ、などと思いつつも、今までの論文修正の稚拙さからして、いくら言っても大して変わらないだろうから、また、その論文で一番大切なのは結果なので、ここらへんは目をつぶることに。ということで、アブストラクトの大幅な修正以外は、図の説明を少々と、本文の表現を数か所指摘して提出。こんな論文に付き合わされるのもたまったものではないが、その間、SAGEのジャーナル(特にFoot & Ankle International)がアクセスし放題なので、よかったと思おう。
2023-10-2:以前2023-6-21締め切りで査読したJournal of Health Sciencesというジャーナルの論文の手直しが出来上がったので、また査読してくださいのメール。10月3日までに査読をするかどうかの返事をしたのちに、10月10日までに査読を提出してくださいと。今これだけ忙しいのに、それはムリ。「今はとても忙しいのでお断りします。締め切りが11月5日までなら喜んで査読します」の返事。
2023-10-4:9月4日に返却したFoot and Ankle Specialist (FAS)の査読に対する修正が再度来たので再査読。ひとつの図だけラベルのつけ間違え。前回の査読でも左右のミスを指摘したのに、どうして一発で直せないのだろうと思いつつ、この点を指摘しながら、Accept after minor revision and without re-reviewとして提出。
2023-10-19:Journal of Clinical Medicineというジャーナルから査読依頼が来た。調べるとPubMedにもJCRジャーナルリストにも載っているちゃんとしたジャーナルのよう。足関節骨折手術の脛腓間スクリューを抜釘した群としない群とのさまざまな指標の比較。学会準備がほとんど終わったし、ちゃんとしたジャーナルのようなので引き受けることに。期限は10月29日まで。
2023-10-29:一昨日足の外科学会は終わり、発表で疲れたので旅程を繰り上げて一昨日のうちに帰宅。足の外科認定医とやらを去年から日本足の外科学会が設定していて、こういうのは取っておかないとあらぬ疑いをかけられるので、面倒だが取っておくことに。昨日すべて書類をそろえて提出しようとしたが、思いの他面倒で、とても昨日一日では終わらず、今朝も朝早く病院に行き、書類をそろえることに。足の外科の症例100例を表にまとめたものと、詳しく10症例についてのレポートを出さなければならない。100症例の方は3時間くらいで出来上がったものの、10症例の方は、1症例につき何だかんだ1時間かかった。夕方になってやっとすべて終わって郵便局で提出。昨日今日でへとへとだが、これから査読をやらなければならない。
まずざっと見るととても長い!それから書いてあることがうだうだと長たらしく、訳わからない。整形外科のジャーナルでこんなに分かりにくかったらすぐにRejectされるはずだが、Journal of Clinical Medicineはこんな調子なのか。もっともらしいことを仰々しく書いているはずが、実は大したことは書いていない、というか書き方があまりに整形外科医っぽくない(整形外科医はもっと単純にできている)ので、著者を調べたところ、学生さんが整形外科に実習に回っているときに書いた論文のようだ(むこうの学生は学生のうちからこうやって論文を書く)。どうりで長いわりに中身がないはずだ。「方法は詳しく、結果は簡潔に」とか「方法と結果とは対応させてわかりやすく」とか指導しないのか。忙しいなら、スタディデザインごとのこういう情報を書く、というようなマニュアルを渡すとか。学生さんはただ一生懸命書いただけなのだが、いかんせん学生レポートっぽいのである。医者は忙しい合間を縫って論文を読むのだから、読んでぱっとわからない論文とか時間の無駄なので読ませないでほしい、っつーか大学ならちゃんと指導しろよ、指導できないなら大学にいるなよ、などとあらゆる文句を言いたくなる。今日は疲れたのでこれ以上取り組むのはちょっと無理。欧米とは時差があるので、明日の朝に書こう。
2023-10-30:朝2時に目が覚めたので早速査読。細かく直すというより、おおざっぱにどこがダメなのかを今後にも生かせる形で伝えた方が良いと思ってコメント。まずは方法のお粗末さがひどいので、こういう順番で書けとか、読者が読んで研究を再現できるように書けとか、いくつかのジャーナルの投稿規定を読んで書き方のフォーマットを身につけろなどをアドバイス。あとはよくある仮説を立ててそれを検証するために研究をデザインしていない点を指摘したり、表を見ればわかる結果をだらだら記述するのはやめろ、とか、まぁそんなアドバイスをして終わった。リジェクトでもよいが、学生なのにやる気をもって論文を書こうとしている若者の芽をつぶすようなことは避けたいので、Major Revisionにして提出した。間に合った。
ついでにメールを見ていたら、エジプトの医学生からメールが来ていた。こちらの出す論文を継続的に読んでいたとのことで、来年4月から研究員として留学したいとのこと。本当?見ると大学のメールアドレスから送っており、その大学を調べたら、西暦700年くらいからある由緒正しいところのよう。どのように返事したらよいものか。
2023-11-16:Journal of Clinical Medicineからメール。修正原稿が来たので再査読して下さいと。見ると、前半の見た範囲ではとてもよく直っている。このようにぱっと修正できるのは好印象だ。
2023-11-22:Journal of Clinical Medicineから査読した論文が無事アクセプトされましたと。
2023-12-28:Foot and Ankle Specialist(FAS)から査読依頼。ちょうど自分の論文を英語添削に出してほっとしたタイミングなのが絶妙。息抜きにはちょうどいいので快諾。
2023-12-31:自分の論文の提出が終わったので、査読開始。関節面が転位した踵骨骨折に対して最初に距骨下関節固定術を行った研究のシステマティックレビュー。まずはシステマティックレビューのガイドラインであるPRISMA読み。
2024-1-4:FASからメール。「最近レビューをお願いしましたが、その必要がないことが判明しました。またの機会にお願いします」と。システマティックレビューだから、方法に特に問題なければアクセプトでいいと編集長が判断したか、査読者の数が充足していたか。正月早々めでたい。
2024-1-6:Exploration of Musculoskeletal Diseasesというジャーナルからレビュー依頼。聞いたことない雑誌だが、スペインの某大学の教授が編集長をやっていて、open accessなのにarticle processing chargeが2028年まで無料なこと(たぶんちゃんとした雑誌に育てるためにそうしているのだろう)や、返事をもらってからアクセスのアカウントを作るなど、割と丁寧なメールの内容だったことから、引き受けることに。著者はスペインの某大学のリウマチ科の准教授。PubMedで調べると、スペイン語論文22本、英語論文7本書いている。スペイン語で論文を書こうというのがえらい。こちらなど、日本語で論文を書いてもどうせ誰も読まないから、そんな努力をするのはまっぴらごめんと思っているが、せっせと書いている。大学向きの人だ。
2024-1-9:Exploration of Musculoskeletal Diseasesから返事。すでに査読者が充足しているのでまたの機会に宜しくお願いします、ありがとうございましたと。まぁ善意だけ売って何もやらなくて済むのはいいことだ。
2024-1-15:Medicinaというジャーナルから査読依頼。見るとアキレス腱症の保存治療のケースレポート。Medicinaというジャーナルは、PubMedにもWeb of Scienceにも登録されている総合誌らしい。ケースレポートの大半はひどいものなので気が進まないが、ちゃんとしている雑誌のようなので引き受けることに。
2024-1-22:1月25日締め切りなのでそろそろやらないと。PubMedで調べたら、Maffulli先生のところで初期研修を終えた5年目の医師で、すでに5本筆頭著者の論文を出しているよう。見ると概ねよく書けているが、ケースレポートなのにディスカッションで大風呂敷を広げてしまっているところなどはよくある粗相。
2024-1-23:査読作業。この論文は日本語論文でよくある「case report and review of the literature」というやつ。この形式の論文はダメ論文の最たるものだと思うが、どうしてこういう論文を書こうと思うのだろう。論文というものは今まで分からなかったことを何かしら解明したからこそ書くものなのに、大して目新しくもないケースをレポートし、それにまつわる文献をただ集めただけで、どうして論文になると思えるのだろう。ケースがダメな分をレビューを加えれば箔が付くとでも思うのだろうか。そんなことならレビュー論文を書けばよい。この論文のディスカッションでも、自分の症例についての言及は一切なく、ただひたすらに文献をまとめるのみ。自分の症例を通じて新たに分かったことはないのか。結局自分では何も考えていないのである。
2024-1-24:査読作業。「case report and review of the literature」という形式の論文の価値には疑問があるが、自分の経験した症例の科学的根拠をしっかり調べることは、著者自身の勉強としてはいいだろう。そういう意味でこういう論文をしっかり書けている著者はそれなりに優秀なのだと思う。背景での問題提起に対して結論が合っていない点や、アブストラクトが叙述的で本文の具体的な内容を十分に反映していない点などを除いては、おおむねよく書けている。しかしこういう「case report and review of the literature」がScimago Journal & Country RankのQ2ランクのジャーナルに載る価値があるかというと別問題。なるべく今後の論文執筆に生かせるようなことを書くことを心掛けながらコメントを完成。recommendは申し訳ないがreject。論文は研究の質が命なのだなとつくづく思う。もう一人査読者がすでに提出していたのでそれを見ると、やはりrejectで、しかも著者へのコメントはかなり強い調子で否定的に書いている。rejectと言われて落ち込むのだから、そんなに強く言わなくてもいいのに。
2024-2-3:Foot and Ankle Specialistから査読依頼のメール。母趾MTP関節の関節固定術の癒合不全に関する研究。まぁ面白そうなので承諾。
査読ではちゃんと読まないと著者に失礼なので、日本語にしてしっかりと理解するようにしている。PDFをGoogle翻訳を使ってそのまま日本語に翻訳すると、行番号などにじゃまをされてきれいな訳にならないので、PDFをWordに変換の後、行番号や文献番号などを削除して体裁を整えた上でGoogle翻訳し、きれいな和訳になるようにしている。査読の初日はこの作業。これさえやっておけば、査読も大した負担ではない。
2024-2-14:論文を読みながら査読のコメント記載。
Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disordersというジャーナルから査読依頼。強剛母趾のヒアルロン酸注射についてのケースレポート。ケースレポートはほとんどがゴミなのは知っているが、強剛母趾の査読を依頼されたのは自分の強剛母趾の論文が認められたからでもあるので、引き受けることに。このジャーナルはSAGEジャーナルで、査読を引き受けると60日間SAGEジャーナルが無料で閲覧できるとのこと。Foot & Ankle Internationalで読みたい論文がダウンロードできるのでラッキー。
2024-2-21:FASの査読の締め切りが明後日なのでやることに。母趾MTP関節の関節固定術の癒合不全に靴の大きさが関係するかどうかを、多変量ロジスティック回帰分析を用いて検証した研究。モデルの適合度に関する記述に若干の不備はあったが、それ以外はおおむね問題がなかった。
2024-2-22:FASの査読。英語のコメントを書いて提出。問題の少ない論文だと査読も楽。
2024-2-26:Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disordersからの査読。読んだら、去年の1月にJournal of Visualized Experimentsというジャーナルからの依頼で査読したスペインの某大学からの論文と同じだった。前回は実験プロトコールという形だったが、プロトコールとしては不備があるのでダメ出ししたところRejectとなったようで、ほぼ同じ内容が今度はケースレポートの形に変わって、別のジャーナルに投稿されたようだ。筆者のスペイン人は前回の実験プロトコール論文に付属していた手技ビデオで見たところ、30-35歳くらいの真面目そうな女性医師だが、一つの論文が中々アクセプトにならず、ずいぶんと苦労しているよう。大学院生で引くに引けないと言ったところか。実験プロトコールとしては不備があるが、ケースレポートならそこまで目くじらを立てる所ではないので、大きな不備がなければ甘めに見てあげよう。
2024-3-8:ジャーナルから査読の提出期限は3月14日だというリマインダーのメール。そろそろやらなければ。イントロの査読。どうして一般的なことをぐだぐだ書いた挙句、いきなり本研究の目的を書くのだろう。論に何のつながりもない。ある疾患の一般的な知見から特定の問題に焦点を絞り、それがまだ未解決の問題であることを書き、その問題を解決するためにどういう仮説を立て、その仮説を検証するためにどう研究をデザインしたのかを書くのはどの論文でも共通のお作法なのに。こんなの論文の書き方本にはいくらでも書いてあることだが、そういうのを読もうと思わないのだろうか。何ならAIに聞けば10秒でおおまかには教えてくれる。腹立たしいのが、これが足の外科で有名な某大学からの論文であることだ。大学ならば指導医がちゃんと添削してからジャーナルに投稿すべきだ。
2024-3-9:査読。文章の論理的な構成力が根本的に欠けているので、確かに必要なことは書いてあるのだが、それがいちいち適切なところではない。こういう組み立ての悪さは、必要なことは書いてあるだけに、悪いということをとても指摘しにくい。こういう人は病院の中でもよく見かけるのですよ。何が間違っているわけではないけれど、何となく仕事が遅れ遅れになってしまう人とか、仕事が求められるものと何かずれてしまう人とか。
2024-3-12:査読。”a case report and review of the literature”という形式で書かれた論文はつくづくダメだと思う。レアケースを報告して、文献をちょっと調べて補強すれば論文になるのだという経験は、今後の論文生活にとってマイナスでしかない。研究というのは、まだ分かっていないことがあって、それを解明するためにするものであるから、まだ分かっていないことをはっきりさせるための文献検索が先にあるものなのに、”a case report and review of the literature”では、行き当たりばったりのレアケースがまずあって、後付けで文献を調べてみました、という論文形式となっており、本来の研究とは逆の思考プロセスになってしまっているのである。初めて論文を書きたいのなら、適切な指導医のもと、システマティックレビューを書くのがもっともよいと思う。どこまで分かっていてどこから先が分かっていないかを調べるという研究の思考プロセスに乗っ取っているし、網羅的な文献検索の方法を学べるし、様々な文献を読むことで、いい研究とそうでない研究はどう違うのかを学べるからだ。今査読しているこの”a case report and review of the literature”も、言いたいことは山ほどあるが、たぶんこの著者の書きっぷりからして今後も研究フィールドに残る人ではないだろうから、記念に1本論文が出ておしまいでいいのではないかと思えてきた。
ということで、基本的にはアクセプト方向に持って行ってあげようとは思いつつも、やはりこんなごたごたに記述している論文は許しかねる。そこで、論文としての最低限の枠組みは満たすため、先行研究から本研究の目的にスムーズにつながるよう、この記述はここに移せ、この記述は冗長で意味がないから削除を検討せよ、目的と結論はきちんと対応するようにせよ、などを書いてほぼ終了。前回、Journal of Visualized Experimentsでこの著者の査読をやった際、この著者はその査読コメントをことごとく無視してきたが、今回はただ並べ替えるだけだから従うだろうか。
2024-3-13:BMC Musculoskeletal Disordersから査読依頼。外反母趾の従来の術式と最小侵襲術式の比較論文。BMC Musculoskeletal Disordersは自分も出そうかと検討しているジャーナルだし、査読をやると自分の論文の出版料を15%割引してくれるとのことなので、承諾することに。提出期限が3月22日まで。数えてみれば、これがちょうど20本目の査読。
Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disordersのケースレポートの方は、昨日査読したものを見直して提出。するとSAGEからお礼のメールが来て、SAGEジャーナルの閲覧を60日無料にしますと。この間に最新のFoot & Ankle Internationalの文献で使えそうなものをダウンロードしておこう。
2024-3-21:査読締め切りが明後日朝(現地時間3月22日)。そろそろやらなければ。基本的によく書けている論文なので、大して直す箇所も見当たらない。
2024-3-22:査読。アブストラクトが大幅に字数オーバーな点や、結果の一部を方法に記載している点以外にはさほど大きな修正点はなかった。
2024-3-23:査読の最後の部分を仕上げてBMC Musculoskeletal Disordersに提出。
2024-3-27:Journal of Clinical Medicineからメール。査読してくれた論文がアクセプトされましたと。どうもこのところ査読の依頼のあるジャーナルを見ると、オープンアクセスかつWeb of ScienceにもPubMedにも掲載されているジャーナルで、必ずしも整形外科雑誌ではない、というジャーナルが多い。上記のJournal of Clinical MedicineとかClinical Medicine InsightsとかBMJ Openとか。散々苦労して足の外科雑誌に出したものの、母体の弱さなのか、まだWeb of Scienceにも掲載されていないなどとなると、がっかりする。どうせどのジャーナルに載ったとしても、検索されるのはPubMedなのだから、変に狭き門を目指して苦労するよりは、上記のような十分な評価がある割に比較的アクセプトされやすく、しかもオープンアクセスのジャーナルを目指した方がよいのかもしれない。
などと思っていたら、今度はScientific Reportsというジャーナルから査読依頼。このジャーナルはあのNatureの母体が出しているオープンアクセスのジャーナルで、やはりWeb of ScienceにもPubMedにも掲載されている。ホームページを見てみたら、方法論が適切であれば結果は問わない、というコンセプトらしい。依頼された論文は7本の論文を集めたシステマティックレビュー。一般に論文数の少ないシステマティックレビューは結果に注意せよということが言われているが、「方法論が適切であれば結果は問わない」というジャーナルのコンセプトに合致しているということか。なるほど。今後の論文提出先の候補にもなりうるので、査読を引き受けることに。
2024-3-31:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery (AOTS)から査読依頼。AOTSはScimago Journal & Country Rankingでも最上位のQ1に属するジャーナル。関節鏡下母趾種子骨切除術についての論文。この内容に関しては自分以上に査読に適した人は世界にいないと思っているので引き受けることに。確かに自分の論文も引用されている。ただざっと見たところ、このくらいの内容でQ1のジャーナルに掲載されてよいのか?
2024-4-3:Clinical Medicine Insightsで査読した、例のスペインの某大学の女医さんの論文の手直しが終わったのでまた査読してくださいとメール。締め切りが5月3日と余裕がある。
4月5日締め切りのScientific Reportsの査読を開始。見るとやたらとよく書かれている。著者の所属を見たらまだ医学生のよう。よほど教育がしっかりしているのだろう。
2024-4-4:Scientific Reportsの査読。メタ解析部も評価しなければならないので大変。
2024-4-5:Scientific Reportsの査読。メタ解析の細かいところは分からないが、選ばれている論文やその結果に問題はないようなので、主に論文の書き方や表現のおかしいところを指摘するのに終始。
2024-4-6:Scientific Reportsの査読。目的と結論がずれてしまうことや本文の結論とアブストラクトの結論がずれてしまうことはよく見かけること。それらを指摘して提出。
2024-4-9:外反母趾の論文を英語添削に出しているので、その間に関節鏡下母趾種子骨切除術の査読。イントロを読みだした瞬間に書き慣れていない著者だということがバレてしまう。一般的なことをダラダラ書き、なかなかその論文のテーマへと焦点を絞っていけない。まぁそれは100歩ゆずってよいとしても、何しろ関節鏡の記載がお粗末すぎる。おそらくちゃんと関節鏡で種子骨を見ることができずに、透視下に適当に削って良しとしているのだろう。実際にやっている身としては、関節鏡のどこが難しいか熟知しているので、そこをごまかそうとしている記述はすぐに分かる。そのあとに術後成績だのディスカッションだの、いくら立派なことを書いてもだめだ。すべては信用のならない方法を前提としているのだから。もうその時点で科学に対して誠実でないのである。
2024-4-10:関節鏡下母趾種子骨切除術の査読。ディスカッション。前半は大して関連性の高くない文献を並べて字数かせぎをしているだけ。最後になって小生の書いた関節鏡下母趾種子骨切除術の論文を取り上げ、それと比較して自分たちの結果も似ていてよかったです、でおしまい。こんな迫力のない論文になってしまう理由は、自分自身の目に自信がないからである。この論文では強剛母趾の症例が5例含まれているが、強剛母趾の母趾種子骨切除など、慣れていない人ではうまく行きっこない(うまく行っていないから術中写真の1枚すら載せていない)。ならなぜ、うまく行かないなら自分たちはうまく行かなかったと書けないのか。人と同じでほっとするような人は論文に向いていないと思う。
2024-4-12:関節鏡下母趾種子骨切除術の査読。査読コメントの整理。人の論文をトレースしたような論文は価値が低いので、いっそ強剛母趾に対する関節鏡下母趾種子骨切除術に書き換えることを提案。こちらのほうがよほど歴史的価値がある。
2024-4-13:強剛母趾に対する関節鏡下母趾種子骨切除術に書き換えることを思いついたが、これは種子骨を内外両方切除しないと成立しないことに後から気づいた。なのでこの案はダメで、この論文はそのままにダメ出ししなければならなくなった。母趾種子骨切除の手技についてまったく記載せずにごまかそうとしている点について、「この場合はどのように鏡視できたのか」「この場合は関節鏡の角度的に見えないはずだがどう処理したか」など、いやらしい質問をたくさんしておいた。こちらの性格が悪いのはさておき、できもしない手技をごまかしながら記載する筆者も悪い。ていうかどうしてできないならできないと書けないのだろう。できないということは手術手技自体の問題かもしれず、それを指摘することでその手技がさらに改良されるかもしれないのに。科学にとって嘘が一番ダメだ。
2024‐4‐14:関節鏡下母趾種子骨切除術の査読が完了したので提出。ただ査読コメントを出せばいいのではなく、題名、アブストラクト、背景などそれぞれの項目ごとにどういう出来か、ジャーナルの用意した質問に答えなければならない。一つ一つ答えると、この論文はだいぶダメな論文であることがはっきりしてしまった。
自分の論文は一区切りがついているし、今日は時間があるので、Clinical Medicine Insightsの例のスペインの某大学の女医さんの論文の再査読。前回具体的にこの記述を消せとかどこに移せとか言ったので、どうやらその通りにしたらしく、ずいぶんと読みやすくなっていた。イントロダクションで一般的な知識から特定の問題へとぐっと焦点が当たる感じが出ているし、ディスカッションではこの論文の結果から出発して他の研究と比較しながら一般化可能かどうか議論が広がっていく感じがよく出ている。ケースレポートでこれなら十分だろう。看過できない点のみ指摘して、あとはアクセプトを推薦して良さそうだ。
2024-4-15:Clinical Medicine Insightsの強剛母趾ケースレポートの査読コメント書き。
2024-4-16:査読し終わったのでClinical Medicine Insightsに提出。
2024-4-29:Archives of Orthopaedic and Trauma Surgeryからメール。関節鏡下母趾種子骨切除術の論文はRejectされましたと。肝心な手術手技の記載をごまかして、さもできたように書くような論文はRejectされてしかるべきだが、難しいなら難しい、できないならできない、と正直に言えないことの科学的な罪深さを、著者たちはこちらの査読コメントから汲み取ってくれるだろうか。別のジャーナルに投稿してもまた自分のところに査読依頼が来る可能性が高いので、そのときが楽しみだ。
2024-5-16:Clinical Medicine Insightsから強剛母趾ケースレポートの修正が終わったので再査読をとのメール。提出は6月13日まで。
2024-5-23:Journal of Clinical Medicine (JCM)から査読依頼のメール。踵骨骨折の普通のプレート固定と最小侵襲手術の治療成績の比較の論文。今はあまり忙しくないので引き受けることに。締め切りが5月29日。
2024-5-27:JCMの査読。原稿を英語のまま査読しようとしたが、長すぎて全体を把握しきれないので、仕方なく翻訳することに。PDFファイルの本文を少しずつコピーしながらWordファイルを作り、Google翻訳を使って翻訳(PDFファイルのままだと行番号にじゃまされてちゃんと翻訳されない)。これでだいぶやりやすくなった。日本語換算で10900語。やはり長い。
2024-5-28:JCMの査読。この著者は1つの事項を2つの段落に離して書く癖がある。わずらわしい。方法と結果が対応していない、結果の提示の仕方も叙述的、結果セクションに書かれていない結果がディスカッションで初出する、など、至る所でごたごた。どうして簡潔に整理して提示できないのだろう。あまりにごたごたなので、著者はどんな人なのだろうと調べてみたら、何とイタリアの某大学の准教授。筆頭著者の英語論文も44本もある。どうしてこんなことになるのか改めて論文を見直すと、おそらく内容の薄いことをもっともらしく書き連ねてボリュームを稼ぐのがうまいのである。はじめはこちらも量に圧倒されたが、日本語に翻訳してよくよく読んでみたら支離滅裂で、とても論文としての体裁をなしていない。しかも、Publishされているジャーナルを見ると、量産型のOpen Accessジャーナルが多い。PubMedに掲載されるも査読者が手薄かつ査読のゆるい新興Open Accessジャーナルにボリュームで圧倒するような論文を大量に投稿しているという訳か。世の中には論文を大して書かずに教授になる人も少なからずいて、そんな人よりはよほどましだが、質の低い論文を大量生産するというのはどうなのだろう。大学に身を置く立場としては背に腹は代えられぬか。
2024-5-29:JCMの査読。致命的な欠陥を発見。この論文は踵骨骨折に対する観血的整復内固定術と最小侵襲手術の治療成績をretrospectiveに比較しているが、これら2つの術式の選択が、ただ何となく術者の好みで各症例ごとに決められているのである。こんなことが許されるのなら、難しそうな症例はすべて観血的整復内固定術、簡単そうな症例はすべて最小侵襲手術、などといった偏向な術式選択も可能となってしまい、こんな分けられ方で分けられた2グループの治療成績をいくら比較しても、どちらがいいとか言えたものではない。ということでRejectを勧めて提出。方法の出発点が間違った論文は、間違った結果や結論を導き出すだけだから、即座にRejectの対象となってしまう。ただ、原稿全体改善すべき点は今後のためにと細かくコメントした。
2023-5-31:Foot and Ankle Specialist (FAS)から査読依頼のメール。FASとはこれからもいい関係を続けていきたいので承諾。
2024-6-2:FASから査読依頼された論文をWordファイル化したのち、Google翻訳して通読。ピックルボールという高齢者用の簡易テニスに関する疫学調査。こういう論文は方法が正しいかどうかだけだからつまらない。あまり訂正するところもない。
2024-6-12:Clinical Medicine Insights: Arthritis and Musculoskeletal Disordersから依頼が来ている例のスペイン某足の外科で有名な大学の女医さんが書いたケースレポートの査読。特に問題なく書けている(というか前回ここはああしろとか相当具体的な手直しを指示した)。Scimago Journal Ranking Q3のジャーナルにこのくらいのケースレポートが載るのは別に問題ないし、著者のスペインの女医さんも去年から相当痛めつけられているのも知っているので、もうOKでいいかと。Acceptを推薦して提出。
2024-6-16:FASから依頼されているピックルボールの論文の査読。こういうつまらない論文を書く人はえらいと思う。誰かが調べないと明らかにならないことだから。
2024-6-17:FASから依頼されているピックルボールの論文の査読の続き。
2024-6-18:査読の続き。この論文が採択されるかどうかは、ピックルボール関連のアキレス腱断裂を興味のあるトピックと考えるかどうかに尽きる。あまり熱心に査読してもお互いに有意義な時間にはならなさそう。さっさと出そう。
2024-6-19:5月29日にRejectのコメントを提出したJCMからメール。修正が終わったので再査読して下さいと。いつも自分が出しているジャーナルなら、ひとりの査読者がRejectと言ったらRejectになるのに、また査読して下さいということは、JCM自体がなるべく載せようとするジャーナルということか。しかも期日が21日までと。「コメントに対してちゃんと対応しているから簡単にチェックできると思います」と。自分の論文も提出したばかりだし、まぁいいか。見ると、さすがに40数本も論文を出している人だけあって、査読コメントに対する修正は徹底的。ほぼすべて書き直すくらいの勢いで書き直している。こちらがRejectの理由に挙げたことに関しては完全に白旗を上げて、Limitationとして記載している。日本人気質からか、白旗を上げた人には何となく寛容になってしまう。
2024-6-20:昨日の査読の続き。統計解析方法でひとつおかしな結論を出しているところを発見。ここは結論に直結するところなので厳しく追及。提出。続いてFASから依頼されているピックルボールのアキレス腱断裂についての論文の査読。こちらはアブストラクトをちょっと書き換える程度。あとは論文そのもののつまらなさを編集長がどう判断するか。こちらも提出。
2024-6-27:Medicinaから査読依頼。アキレス腱断裂のオープン手術と経皮的手術の比較論文。題名を聞いただけでつまらなそうだが、今は比較的余裕があるので承諾。
2024-6-28:アキレス腱断裂の論文の査読。単に治療成績をまとめただけで、特に目新しい知見があるわけではない。ディスカッションも他の研究の治療成績と同様であることを確認しただけ。こういう努力をする人ってよくわからない。新たな知見を世に知らしめてアッと言わせようといったワクワクもドキドキもなく、単に他の人と同じ結果でした、と述べるだけの論文を書いて楽しいのだろうか。
2024-6-29:Journal of Orthopaedic Surgery and Research(JOSR)から査読依頼。外反母趾の経皮的手術とオープン手術の治療成績の比較論文。JOSRはちゃんとしたジャーナルなので引き受けることに。7月8日締め切り。
2024-7-1:Medicinaの査読。結果の提示のごたごたさや、データの無意味な棒グラフ化などが気になる。「統計的に有意」という言葉を簡単に使っているが、どの統計的手法を用いて解析しているのか記述が曖昧。
2024-7-2:BMC Musculoskeletal Disordersから査読依頼。いつも論文を出しているジャーナルと同レベルのジャーナルなので快諾。踵骨骨折の手術法に関するもの。結果、今すべき査読が3つになってしまった。期日の一番近いMedicinaの査読を終了。あまり問題は少ないが、箱ひげ図で示すべきところを棒グラフで示していたり、円グラフで示せば一目でわかることをダラダラ記載していたりするところなどを指摘。ていうかそもそも、オープン手術と経皮的手術の治療成績の比較といったありふれた研究を今更出す必要があるのかという点もあるが、それは編集長に判断してもらおう。
Journal of Clinical Medicine(JCM)からメール。「今度”Clinical Perspectives on Foot and Ankle Surgery”というトピックで特集号を作ろうと企画していますが、ゲスト編集者になりませんか」と。JCMはPubMedやWeb of Scienceにも登録されているし、Scimago Journal Rankingでも総合誌のQ1にランクしているジャーナル。ゲスト編集者は、こちらのアイディアに従ってトピックを調整したり、特集号の目的や範囲を定義したり、寄稿の募集と事前チェック・最終決定などをするとのこと。さらに、ゲスト編集者自身の論文と、ゲスト編集者が招待した3本の論文は論文処理料が無料になるとのこと。とてもよい話だが、急な大役でめまいがする。今まで論文を書き、そこから査読者としての実績も積み重ねてきたので、次の段階としてはゲスト編集者ということになるだろうか。とりあえずやってみないと分からないし、論文もタダにしてくれるとのことだから、引き受けてみよう。
2024-7-3:JCMの編集部から返事があり、1週間以内にトピックをカバーする200語の短い要約と6-10個のキーワードを返送せよと。どういうテーマにするかしばらく考えよう。JOSRから依頼の外反母趾の経皮的手術とオープン手術の治療成績の比較論文の査読。自分の論文は仕事から家に帰ると疲れてやる気が起きないが、人の論文の査読は突っ込みどころを探すだけなのでできる。やはり、一から自分で作るのと作られたものを批評するのとでは、頭を使う量が違う。
2024-7-6:JOSRから依頼の外反母趾手術のオープン手術と経皮手術の比較論文の査読。問題なのは、フォローアップが6カ月しかないこと。その時点でこちらの術式のほうがよい、というのが、臨床的にどれだけ意味があるのだろう。しかもその差もわずかだ。多くのジャーナルが術後2年以上のフォローアップを必須としているのは、やはり短いフォローアップでは治療効果を評価できないと認識しているのだからではないのか。JOSRのようなそれなりに評価されるジャーナルがこんな論文をアクセプトしていいのか?
2024-7-7:JOSRの査読。おおむね良く書けた論文だが、フォローアップ期間が6か月と短すぎるので、いったんこの論文は撤退して、術後2年までデータを積み上げてから再提出すべきだと書いて提出。続いてBMC Musculoskeletal Disordersから来た踵骨骨折の治療成績に関する論文の査読。ちゃんとデータを取って実直にまとめている。マイナーリビジョンすべきところはあるだろうが、基本アクセプトの方向でいいのではないか。
2024-7-8:JCMから依頼の来た特集号の編集者に関して、返信用のファイルを見ると、サマリー、キーワード、推薦する著者、編集者情報サイトなど、記入すべきことが沢山ある。これをあと3日でするのはとても無理だし、サマリーはそのままジャーナルサイトに載って記事を募集するのに使われるので、いったん作ったら英語添削にも出す必要がある。期日を7月22日に延期してもらえるようメールの返信。
BMC Musculoskeletal Disordersの査読。いい治療成績で、しっかりデータを取ってあり、フォローアップも5年以上、特に言うことのない論文。共著者もそれぞれ役割分担がはっきりしていて、全員が最終的な論文に目を通してサインしたと。中国の市中病院からの報告で、こういうちゃんとした論文は前にも見かけたような気がする。
2024-7-9:BMC Musculoskeletal Disordersの査読。それにしても修正すべき点がない。おそらくこの論文はFoot & Ankle Internationalあたりに一度投稿し、厳しい査読を経たのちに、そもそもネタがつまらないなどといった理由でRejectされた論文なのではないか。前の査読に従って修正したのちにこのジャーナルに出してきたから、ほとんど直すところがないのだと思った。Abstractの中に出どころ不明な数値があったので、そこだけ指摘して提出。あまりにコメントが少ないとちゃんと読んでいないのではと思われてしまうが仕方ない。
2024-7-10:Journal of Orthopaedic Surgery and Research(JOSR)からメール。前回のことかと思ったら、また新しい査読依頼。最近の、朝は自分の論文をやり、夜は人の論文を査読する生活は割と気に入っているので承諾。内容は、踵骨骨折の創外固定と距骨下関節鏡併用の経皮的手術に関するもの。昨日査読したものとあまりに似通った内容なので著者を見てみたが、同じ中国でも全く別の施設からの報告。
2024-7-11:JOSRとBMC Musculoskeletal Disordersからまた査読依頼。それにしても頼みすぎだろ。JOSRは外反母趾手術のラーニングカーブに関する論文。BMCは人工関節手術における術前アルブミン値と輸血の関係に関する傾向スコアマッチングでの比較論文。前者は足の外科領域で、後者は統計的な問題でなかなか査読者がつかないのだろう。なんだか楽しそうなので承諾。これでしばらくは夜やることに事欠かない。
2024-7-12:Journal of Clinical Medicineからまた査読依頼。ここ数日査読依頼が多すぎる。まぁいいか。承諾。
2024-7-13:JOSRの査読。踵骨骨折の治療成績。そんなに問題のない書き方だが、いかんせん新奇性に乏しい論文はアクセプトされるべきなのだろうか。とりあえず書いて提出。だいぶ査読が速くなってきた。1度目はゆっくりと読みながらコメントを書いていき、2度目の読みで変なコメントではないかのチェック。終わったらCopilotで「私は英語が母語でない話者です。私の書いた以下の文をよりナチュラルな英語に改訂してください」と書くと、きれいな英語に変換される。
2024-7-14:JOSRから依頼されたもう一つの論文:外反母趾手術のラーニングカーブに関する論文の査読。Bayesian change point modelとかいう統計的手法を取っているが、これについて全く知識がないので勉強せざるを得ない。
2024-7-15:BMC Musculoskeletal Disordersからの査読。人工関節手術における術前アルブミン値と輸血の関係に関する傾向スコアマッチングでの比較論文。おおむねよく書けている。中国の比較的大きな市中病院からの論文はよく書けているものが多い。たぶんちゃんと指導しているのだろう(国からも研究資金をもらっているし)。1施設で人工関節10年間で2500件というのも中国らしい。
続いてJOSRから依頼のベイズ分析を用いた外反母趾手術のラーニングカーブの論文の査読。スペインのトップクラスの大学の准教授先生の論文だが、偉かろうがなかろうが、こちらが直すべきだと思うことは臆せず言えるのが査読のいいところ。題名を小洒落た感じにしているが、科学的でなく読者に誤解なく伝わらないので、躊躇なく修正するよう指摘。書き慣れている人だけあって、他はさすがにしっかりした記述。ベイズ統計学を振りかざしてラーニングカーブのフェーズに関して恣意的でない判断ができるなどと言っているので、最初に著者自身が3段階にフェーズを設定して解析した始めたのは恣意的ではないのですか、とも指摘。まぁいずれの論文も最終的にはアクセプトだろう。
今日は朝から査読をやって結局夜までかかった。中々自分の論文が進まない。
2024-7-16:最近、母趾種子骨骨折癒合不全に悩むカナダ人の方とのメールが続いているが(その方は関節鏡下自家骨移植術の論文を読んでメールしてきた)、その返信をしてからJCMの査読へ。機械学習などの最新の機器を駆使しているのはわかるが、三次元的な変形である扁平足の診断を、レントゲンの側面像だけから診断しようとしている点がそもそもいただけない。いろいろな方向から撮影するのはそれぞれ評価するべき項目があるからであって、それらと臨床症状を加えて総合的に診断する必要がある。著者は放射線科の先生で、患者さんから訴えを聞くことなく画像だけからものを言わなければいけないので、そこがつらいところ。さまざまな評価をすべき扁平足のレントゲンに関し、側面像のある角度だけを精確に測定するソフトを作ったところでそれは臨床家にとって意味をなさないので、申し訳ないがRejectを勧めて提出。ていうか研究を始める前にちゃんと整形外科医と話し合うべきだ。
2024-7-17:依頼されていた査読はすべて終わったので、JCMから依頼された特集号のゲストエディターに関する作業。まずは特集号のテーマ決め。「Foot & Ankleの最小侵襲手術」にしようかと考えたが、最小侵襲手術と書くと、ただ傷だけを小さくしだだけで実は侵襲の大きい外反母趾手術や強剛母趾のカイレクトミーなど、自分の好きでない手術も含まれる可能性が高いため、「Foot & Ankleの革新的手術」にすることにした。そうすれば発想勝負になるし、小さなアイディアも拾うことができて面白いだろう。ひとまず最近のFoot & Ankle のジャーナルに目を通し、「これは革新的だ」と思える論文を探してみよう。期日は7月22日。まずはFAOを最新号からさかのぼって検索。中々斬新な術式は見当たらない。
2024-7-18:JOSRからまた査読依頼。今度はJOSRの編集長で足の外科では世界的に有名なMaffulli先生の名で来た。Maffulli先生からの依頼とあれば受けざるを得ない。テーマは強剛母趾の人工関節失敗後の関節固定術について。強剛母趾は末期であろうと、うちでやっているような簡単な骨切りで良くなるのに、世界ではこんなことになってしまっている患者さんが沢山いる。早くEFORT Open Reviewsに投稿した強剛母趾のレビューが世に出てほしい。
2024-7-20:JCMの特集号の書類書き。FAOを見て執筆候補者選び。ちょっとでも面白そうな記事はすべてピックアップ。
2024-7-22:JCMの特集号のための執筆者候補選び。Foot & Ankle International, Foot and Ankle Surgery, The Journal of Foot and Ankle Surgery, Foot & Ankle Specialistの過去6年分の論文を見て、面白そうな論文をピックアップ。とりあえず最近の面白いネタは集まったので、それを踏まえてどのようなお題にするのが最も論文が集まりそうか検討。JCMの特集号を組んでいる他のEditorの募集メッセージの閲覧。
全然関係ないが、昨日お問い合わせフォームから来たメールに返答するも、メールアドレスの誤記入か、メールの設定がHotmailからのメールをブロックしているかで届かず。メールが届かない理由のほとんどはこの2つのどちらか。これ以上にその方に連絡する手段もなし。たぶんあちらは、こちらが問い合わせメールを見落としているとか無視しているとか思っていることだろう。
2024-7-23:JCMの執筆者候補選び。せっかく執筆者候補に選んでも、連絡先が書かれていない人もいたり、またORCIDの記載がいい加減な大学所属者もいたりする。大学に所属して科学のフィールドでやっていこうとしているのに、自分の業績が他の人に見えるようにしていないとはどういうことなんだ? そういう人は招待してあげない。とりあえず論文を募集するための告知文やキーワード、執筆者の候補のリストなどを完成させ、JCMの係の人に返送。
続いて、JOSRから依頼の査読。強剛母趾への人工関節失敗後の関節固定術の治療成績。特に問題なく書けているが、つまらない。人工関節が失敗した症例に後から関節固定術をしましたが、良好な治療成績でしたって。。まぁどこかのジャーナルからpublishされるべき内容なのだが、27人もそんな患者さんが出たら途中で反省しろよと言いたくなる。
2024-7-24:査読を仕上げてJOSRに提出。書いた査読をCopilotに「よりナチュラルな英語に改訂してください」と入力して、添削してもらってから提出。おかげで自分の書いた英語に自信が持てるようになった。
続いて、7月1日にMedicinaに提出したアキレス腱断裂の論文の再査読。前回無意味な棒グラフを「箱ひげ図に書き換えよ」とコメントしたが、単に棒グラフを消しておしまいにしていた。箱ひげ図は統計ソフトのグラフ作成機能では描けないでしょう?自分で描くんですよ。だいたいグラフといういかに他人に分かりやすくプレゼンするかという部分を、標準のグラフ作成ソフトに頼っていいはずがない。自分でIllustratorで描かないと。他に、表もいまいち。表のレイアウトも考えて描かないと。表について色々指摘して、今一つな修正をされてまた指摘するのはわずらわしいので、結局作ってあげてしまった。
2024-7-25:Medicinaに査読コメントを送信。とりあえずやるべき査読はすべて提出した。
2024-7-26:またJournal of Clinical Medicineから査読依頼。足関節骨折での脛腓間スクリューは抜釘すべきかというシステマティックレビュー。
7月16日に査読を提出したJCMから、修正後再査読依頼。前回はRejectを勧めたのに再査読せよとは。。要はこの論文をエディターはアクセプトにしたいのだろう。まぁいいや。3日以内にOKかどうか返事せよと。
2024-7-27:JCMから催促のメール。アクセプトの評価にして提出しようとも思ったが、そうするとこちらの査読にあまりに一貫性がないので、前回Rejectの評価をしたのにこの論文を再査読するのは適していない旨を書いて返送。