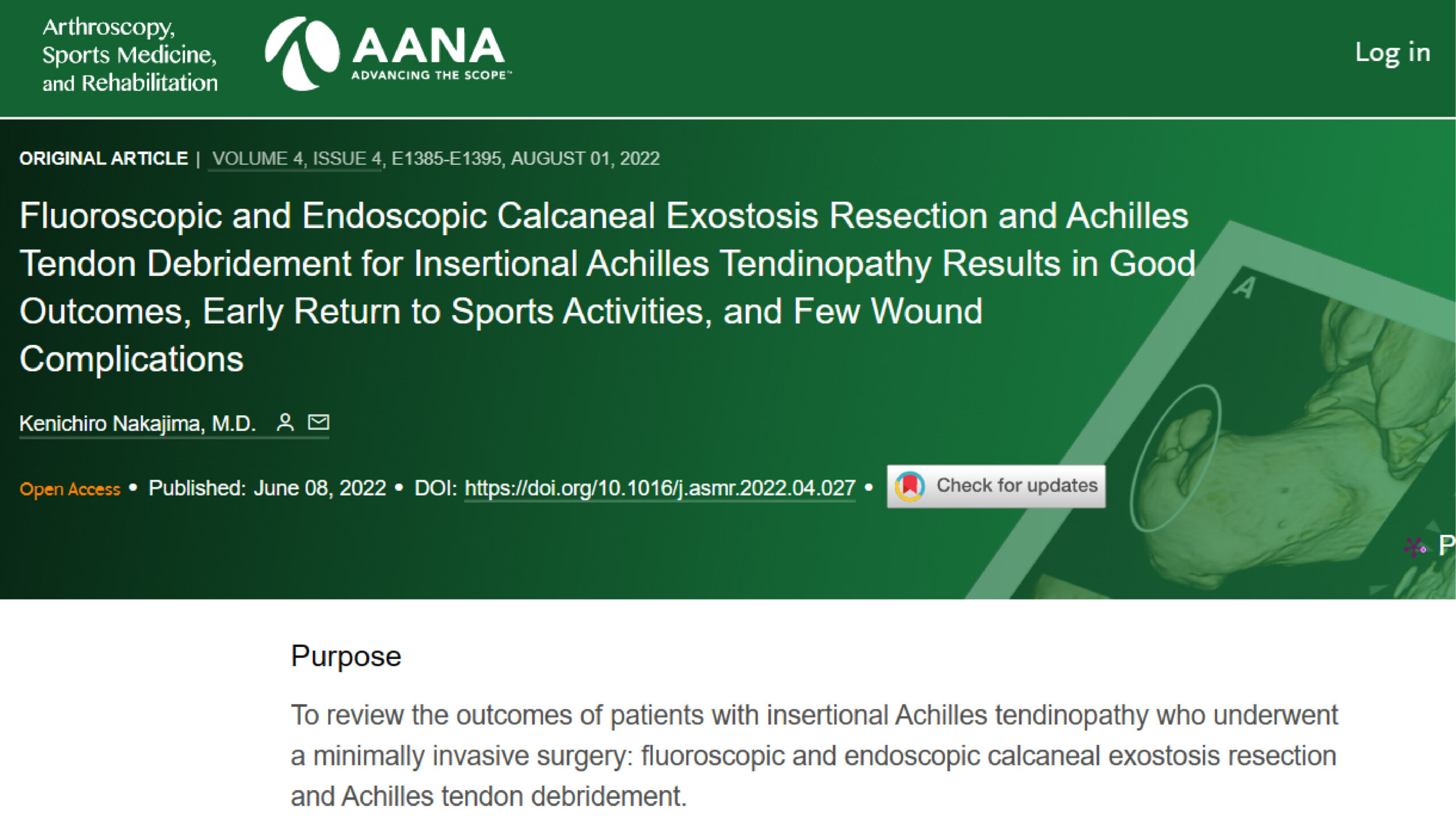概要
当院で行っているアキレス腱付着部症に対する内視鏡手術の論文です。2022-4-25に雑誌Arthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation(ASMAR)にアクセプトされました(論文はこちら)。その後、手術ビデオを雑誌Arthroscopy Techniquesに投稿し、2023-2-12アクセプト(論文はこちら)、さらにWorld Journal of Orthopedicsから依頼を受けたアキレス腱付着部症の最小侵襲手術に関する解説レビュー記事を提出し、2023-5-9にアクセプトされました(論文はこちら)。
なお、臨床評価としての”PASS”や”MCID”の用語を検索してこちらに来られた方は、この論文内の統計処理の記述や、そこで引用されている文献、2022-3-26の日記などを参照していただくと理解しやすいかと思います。
経過
2021-3-19:着手。
2021-3-24:文献の表を作る。
2021-3-25:文献整理のためにMendeleyを導入。
2021-3-26:研究計画書の提出。
2021-3-30:文献検索
2021-4-18:質問票の作成。評価項目はVAS、JSSFとVISA-Aに。
2021-4-19:質問票の作成。
2021-4-20:Mendeleyで文献読み。
2021-4-22:住所録作り。術前の状態をEXCEL入力。質問票の作成。Amazonから封筒などが届く。
2021-4-27:アンケート封筒準備。
2021-4-28:アンケート郵送の準備。
2021-4-29:祝日を利用して、アンケート郵送袋詰め。足底腱膜炎のアンケートと合わせて7時間。
2021-5-7:アンケート返送が次々に届く。
2021-5-17:アンケートの点数化。
2021-5-23:文献のPDF化 。
2021-5-27:文献のPDF化 。
2021-5-28:Mendelely読み 。
2021-5-31:Mendeley読み。総説。
2021-6-7:データまとめ。
2021-6-8:データまとめ。
2021-6-28:データ整理、執筆。
2021-6-29:データ入力。
2021-7-31:データ解析。
2021-8-1:データ解析。8月中に出そうと決意。
2021-8-2:方法の部分を執筆。
2021-8-3:データの読み返し。VISA-Aも追加できるか検討。
2021-8-4:アンケートの点数化。
2021-8-5:執筆。
2021-8-6:ほぼ執筆終了。
2021-8-7:引用文献の選定。
2021-8-8:画像作成。
2021-8-9:画像作成。Illustratorを初めて使用。 3Dペイントよりずっと便利。
2021-8-10:原稿の推敲。
2021-8-11:原稿の推敲。Kindle足の外科教科書でのキーワード検索。
2021-8-12:原稿の推敲。Kindle内のMann、Campbell、統計の本のキーワード検索を使って。
2021-8-13:原稿の推敲。引用文献部(最終)。著者+発行年度の記載で楽に。
2021-8-14:原稿の最終的なチェック。
2021-8-15:Abstractを作成。
2021-8-16:グラフの作成。EZRからIllustratorに張り付けて作成。 グラフというのは作成者が意図の反映なのだから、自動的に作成してくれるソフトでなく、Illustratorで強調部分を考えて作る方がよいのだと分かる。
2021-8-17:英語添削会社Enagoに提出。
2021-8-18:AJSMへ提出に必要な書類の整理 。
2021-8-21:AJSMに提出。提出の煩雑さに嫌気がさす。
2021-9-10:AJSMからreject通知(査読に回される前の門前払い)。「サンプルサイズが小さく限られた読者にしか興味がない」ため。
2021-9-12:Arthroscopyに提出するために原稿の手直し。
2021-9-13:Enagoに提出 。
2021-9-17:Enagoから返却。Arthroscopyに投稿。
2021-11-6:Decision in Processからwith Editorに。
2021-11-16:再びDecision in Processに。
2021-12-30:雑誌ArthroscopyからRejectの通知メールが届くも、姉妹雑誌のArthroscopy, Sports Medicine, and Rehabilitation(ASMAR)へのRevisionに招待される。Arthroscopyの姉妹雑誌だし、PubMedにも載るし、格安でOpen accessになるので喜んで受諾。
2022-1-1:査読内容のチェック開始。
2022-1-2:査読コメント読む。論文の書き方に関して多くの修正は求められるも、論文そのものに含まれる大きな問題点は指摘されなかった。ということは、ArthroscopyにRejectされてASMARに回った理由は、ひとえに研究デザインが「ケースシリーズ」だということのよう。
2022-1-3:査読コメントの再読と対応の検討。
2022-1-5:査読コメントの再読と対応の検討。
2022-1-6:査読コメントの再読と対応の検討。論文作成の過程で今がいちばんきついとき。
2022-1-10:査読コメント再読と対応の検討。しばらく空いてしまったが、そろそろ本気で取り掛からないとまずい。。全部で54個の指摘。
2022-1-11:査読コメントに対する返答と論文の修正。
2022-1-12:査読コメントに対する返答の原稿づくり(日本語)。
2022-1-13:査読コメントに対する返答の原稿づくり(日本語)。
2022-1-14: 査読コメントの整理。整理したことで、54個のコメントに基づいて修正すべき点が一望できるようになってきた。
2022-1-15:査読コメントの見直し。どの順に対応するか検討。
2022-1-17:査読コメントに対応した論文の修正。
2022-1-18:査読コメントに対応した論文の修正。いよいよ本格的に修正の開始。
2022-1-19:査読コメントに対応した論文の修正。2時起床。論文がはかどるかどうかは、ひとえにどれだけ早起きできたかによる。
2022-1-20:査読コメントに対応した論文の修正。どう修正するか考える時間が必要なため、すぐに修正できないことも多い。
2022-1-21:査読コメントに対応した論文の修正。Discussionは大幅修正のため段落構成を組み直し。
2022-1-22:論文の修正すべき箇所をもう一度まとめ直し。複数の査読者から似たような指摘を受けているので、整理をしないとわからなくなる。
2022-1-23:修正すべき箇所を、Abstract, Introduction, Methods, Results, Discussionごとにまとめ直し。手あたり次第修正して、セクション内のバランスが崩れるのは避けたい。
2022-1-24:各セクションごとの修正箇所の確認。統計的な修正箇所の勉強。
2022-1-25:統計的な修正箇所の勉強。MCID(minimal clinically important difference)とPASS(patient acceptable symptomatic state)のデータを出すよう要求された。MCID、PASSともに初めて聞く言葉。MCIDはスコアの差の1/2標準偏差を超える改善を示すサンプル数の割合、PASSは最終的に手術してよかった思っている患者さんの臨床評価値(VASとか)の75パーセンタイルの値で、それを達成したサンプルの割合で示すらしい。
2022-1-26:論文の修正。各セクションごとに修正箇所をまとめたのが有効。修正すべきことが一望できる。MCIDとPASSについて文献検索。記載の仕方を参考にしたり、引用文献に載せたり。
2022-1-27:Discussionの大幅な書き換え。
2022-1-28:Discussionの英語の手直し。各段落ごと。
2022-1-29: Discussionの英語の手直し。各段落ごと。
2022-1-31: Discussionの英語の手直し。各段落ごと。
2022-2-1: Discussionの英語の手直し。各段落ごと。 最終段落。
2022-2-2:Discussionの見直し。英語がアメリカ人好みの論理的な文になっているかどうかが気になる。
2022-2-3:載せるように言われた図と表の作成。図の説明。
2022-2-4:方法の記述のしかたを見るため、ASMARの他の論文を読む。open accessなので自由に読めるのが便利。
2022-2-5:ASMARの他の論文読み。Case-series自体少ないため、まだこれと言った論文に出合わない。
2022-2-6:ASMARの他の論文読み。形式では参考になることがあるも、MCIDやPASSを使った論文には出合わず。しかたないので、PubMedで、これまでASMARでPublishされた論文のうち、MCIDやPASSを使っている論文を調べると、3個しかない。これでは出合わないはず。1つ1つ拾ってMendeleyへ。
2022-2-7:MCIDとPASSを取り扱った論文読み。どう解析すればいいのか、まだピンと来ていない。
2022-2-8:MCIDとPASSを取り扱った論文読み。もう一度患者さんにアンケートを出す必要があるかどうかの判断のため、もう少し理解を深める必要あり。PASSのthresholdの算出に、ROC曲線を利用するというのもよくわからない。
2022-2-9:一日経ったらPASSの閾値にROC曲線を使う理由もあっさり解決。閾値を厳しくすれば特異度は良くなるが感度は悪くなり、甘くすればその逆になる、そこでROC曲線を使って程よい閾値を選ぶ、というだけのことだった。ほかに、全サンプルのうち厳しめの値から75パーセンタイルの値を閾値にするという方法もあり、どちらにするかは決めかねる。患者さんにアンケートを再郵送する必要があるか検討するため、もう少しMCIDとPASSの論文読み。
2022-2-10:MCIDとPASSのキーワードで検索して出てきたopen accessの論文を読み続けているうちに、だいたいやりかたは理解できた。整形外科系の雑誌はあまりちゃんと統計手法が書かれていなかったが、Journal of Clinical Medicineに載っている論文はしっかりと記述されていたので、これを参考にすることに。患者さんからのアンケートを読み返したところ、ここからの情報で何とかなりそう。
2022-2-11:患者さんのアンケートを見て追加集計。術後の状態に満足しているかどうかを読み取ってyes/no評価し、それを用いてPASSを計算。75パーセンタイルによる算出法の方が簡単かと思いきや、ROC曲線の方が統計ソフト一発で出してくれるので楽。さらにMCID, PASS部の論文記述。
2022-2-13:一昨日の祝日に根詰めてやり、あまりに疲れたので16時から昼寝をしたら、起きたのが朝7時(笑)。なので昨日はやらずじまい。今日は気分新たにMCIDとPASSの追加計算。MCIDとPASSの文献を読み比べて、自分の論文での表現を推敲。
2022-2-14:ひとまず大きな訂正は終わったので、全体の通読。細かい点の修正。半分以上書き換えているので、一通り見直すだけでもすぐには終わらない。
2022-2-15:参考文献の整理。文献の順番の入れ替え・追加・整理しかしていないのに、優に3時間以上かかる。Wordの番号を振る設定がうまくできず(連番がどうやっても切れてしまう)。しかたなしに手書きで番号振り。図の番号の振り替え。追加を指摘された図も何とか入れられた。図の説明の追加。
2022-2-16:図の改訂。要求された図を載せるべく、今まで分けていた図を一つの図にまとめたり、内視鏡写真を差し替えて構造物に記号を振ったり。それに応じた図の説明の修正。とりあえず一通りの修正が終了。最終的な見直し:タイトル、アブストラクト、方法、結果のセクション。
2022-2-17:最終的な見直し:ディスカッション。文と文の関係を確認して、変な論理展開をしていないかチェック。図の説明も。原稿の修正は終了した。カバーレターと査読コメントに対する返答書き。
2022-2-18:査読コメントに対する返答書き。全部で54個。答えるのが難しい数個を除いてひとまず書いた。
2022-2-19:査読コメントに対する返答書き。残った面倒なお題も、朝だとすぐに対応する気になる。ひとまず終了。あとは査読コメントでの要求にちゃんと応えられているか、本文の修正箇所と返答を見直し。
2022-2-20:査読コメントの返答と修正箇所の見直し。①返答がコメントに対してちゃんと答えになっているかどうか、②本文の修正がコメントの要求に応じたものになっているかどうか、チェック。カバーレターの作成。以前他の論文で使ったカバーレターをちょっと書き直して使用。とりあえず終わったので、修正した原稿とカバーレター&査読コメントへの返答ファイルを、英語添削会社enagoに送った。何日かヒマになるので、足底腱膜炎の論文に移ることに。
2022-2-21:enagoからメールがあり、「英語の質に対するコメントを査読者からもらったことは、重要な懸念事項と考えています。調査部門で検討してから対応を提案します。」とのこと。しばらく時間がかかるかも。
2022-2-22:enagoからまたメールが来た。「前回添削した原稿(=雑誌に投稿した原稿)の中で2カ所小さな見逃しがあった」とのこと。これも踏まえて一昨日提出したファイルの添削を開始しますと。2/26が納品日。
2022-2-24:利益相反の開示フォームのPDFを編集できないようにせよ、とアシスタントエディターのコメントにあったので、添削が戻ってくるまでにやっておくことに。PDFについてもっと理解する必要あり。
2022-2-25:PDFファイルの「印刷」を押し、プリンタで”adobe PDF”を選択、そのまま印刷実行ボタンを押すと、別のPDFファイルの保存が要求される。このファイルがどうも編集不可能なPDFファイルらしい。容量を見ると1.2MBが100KBくらいになっている。おそらく印刷のために編集機能などをそぎ落としたファイルなのだろう。とりあえずこれで提出することに。
2022-2-27:enagoから返却された添削をチェック。ASMARから最初の投稿論文に対する変更履歴はすべて残すように指示されていて、今回のenagoの添削で、自分が変更した履歴の上にenagoによる変更履歴をどうかぶせるか興味津々だったが、見事に自分が変更した分の履歴は消されていた(笑)。まぁそういうのは仕方ないので、添削されてきた結果をもとの原稿に「自分で」書き加えることで、両方の変更履歴を残すようにしなければならない。
2022-2-28:原稿の修正。添削に従って。OneDriveとデスクトップ上のファイルの連携が不調らしく修正が反映されないため(いったん閉じて開くと直っていない)、同じ修正を4回繰り返し疲れ果てる。表現に関する修正点については終了(内容上の修正点はまだ)。
2022-3-1:今回の添削内に、査読者のコメントに対する修正の不備の指摘があった。査読者のひとりはおそらく英語非ネイティブ(他の箇所の英文法ミスから非ネイティブかと)で、コメントのひとつの英語が何を言っているのかよくわからず、おそらくこういうことを言っているのだろうと推察して対応したが、その推察が違っていたよう。添削者は、その査読者の言わんとするところを想像してくれていたが、そう言われれば確かにそう読める。その修正。
2022-3-2:ディスカッション内の、既存のHaglund変形に対する内視鏡手術と今回のアキレス腱付着部症に対する内視鏡手術の違いに関する記述がごちゃごちゃしていたので、その文の整理。自分の言うべき点が9個あり、それらの表現の仕方と文の順序を入れ替えた。いちおう納得できる形にはなったか。指摘された引用文献の欠落箇所の修正。
2022-3-3:アブストラクトが字数オーバーになっていたので、その短縮。略語はもとの形を書くべきだが、the Victorian Institute of Sport Assessment self-administered Achilles (VISA-A) questionnaire scoresとか書くと、それだけで7語も余計に取られてやってられない。スペルアウトしたところでVISA-Aの質問内容が分かるわけではないし、VISA-Aといきなり書いている論文のアブストラクトも多かったので(たぶん皆同じ悩みだろう)、スペルアウトしないで押し通すことに。enagoで直されるか。査読コメントへの回答ファイルもさらに修正し、再びenagoに添削依頼。3月6日朝6時に返却予定とのこと。
2022-3-6:今朝添削ファイルが返ってきたので、さっそくそれを見ながら原稿の修正。原稿が出来上がったところで、査読コメントへの回答ファイルに、原稿の中で各コメントに対する修正がどの部分かを示す行番号を記入。この行番号の記入でひどい目に遭った。提出原稿のWordファイルには修正履歴を含めるように言われているが、この修正履歴があると、Wordファイルの行番号が、表示する画面の大きさによって変わってしまう。査読コメント(54個)への回答ファイルに行番号を記入していって、後半になって何だかおかしいとようやく気付いた。どうしたら安定した番号になるのかと思って試行錯誤したところ、修正履歴を表示/非表示にすることができることに気づき、非表示にすると行番号が安定するとわかった。そこで、修正履歴を非表示にした状態で、行番号を全部振り直し。ようやく出来上がってASMARに投稿したところ、最後に再び査読者にまわるPDFファイル(修正原稿、図、査読コメントへの回答などがすべてひとつのファイルになったもの)を確認するのだが、そのファイルを見ると、原稿の修正履歴がすべて表示されている!…ということは、確認のPDFファイルを見るまで行番号は決まらない、ということではないか。吐き気を催しながら、そのPDFファイルを見つつ査読コメントへの回答ファイルの行番号をふたたび全部振り直し。その回答ファイルをアップロードしなおし、ようやく問題のない再提出PDFファイルになった。やっと再提出完了。計12時間かかった。とりあえず再提出できたので、明日からはまた足底腱膜炎の論文へ。
2022-3-7:昨日提出した原稿のPDFを再チェックすると、題名に関係するところで修正しきれていないところを4か所も発見。題名も含め、原稿に含まれるspur(骨棘)をすべてexostosis(骨の突出)に直すように編集長から言われていたが、初回に提出したときに提出サイト上に残っていた元の題名や、自分の出したタイトルページなどに直していないところを4か所も見つけてしまった。昨日のあの疲れ具合では仕方がないか。まぁ修正するチャンスはあるけれども。
2022-3-9:ASMARのサイトで自分の提出論文の進行状況をチェック。”Current Status”は”Revision Submitted to Journal”のまま。そうそうすぐに進むわけがないか。
2022-3-10:”Current Status”が”With Editor”に。早い。
2022-3-13:”With Editor”のまま。
2022-3-19:”With Editor”
2022-3-26:”MCID”、”PASS”、”治療成績”でGoogle検索すると、この論文日記が意外と上位に来る、という情報をget。やはり統計処理に悩む整形外科医は多いのだろう。そこでちょっと解説しておくと、まず「MCID(minimal clinically important difference)」とは、「手術で『改善』した患者さんの割合」を示す指標。術前・術後のスコアの差の標準偏差の1/2を計算し、それを超えて改善した患者さんの割合を出す。これは簡単。一方、「PASS(patient acceptable symptomatic state)」とは、「手術して現在『満足な状態』になっている患者さんの割合」を示す指標。いくら手術で症状が「改善」したからといって、それが「満足な状態」かどうかは別問題、ということで、MCIDとPASSは「相補的」な指標。「満足な状態」になっているかどうかだから、単に満足/不満足をアンケートして、それで割合を出せばよい、というの「ではなく」、満足/不満足という「主観的な指標」と、「実際のスコア」とを結びつけようとしたところが、このPASSの概念のすごいところ。すなわち、「満足/不満足」の結果を検査の「陽性/陰性」に見立て、それと実際の術後スコアとの「関係」を調べるべく、両者のデータをROC曲線を用いて解析(統計ソフトで計算)し、満足/不満足の「閾値」を算出(=感度+特異度がいちばん高いところを閾値とする)。そうして得られた閾値を超えてよくなった患者さんの割合を数える。なお、アンケートの手法として、「満足ですか不満足ですか」では極端すぎて患者さんは答えに困るので、「満足/やや満足/どちらでもない/やや不満足/不満足」の中から選んでもらい、上位2つを満足、それ以外を不満足とする。
2022-3-27:”With Editor”
2022-4-3:”With Editor”。あいかわらず遅い。
2022-4-10:”With Editor”。。
2022-4-12:”Current Status”が”Decision in Process”に。
2022-4-15:編集長からメール。前回のrevisionを”great job”と評価してもらった。あとは言い回しをこう修正せよとか、図に矢印を入れよとかいった”minor revision”を14カ所指摘されていた。アクセプトが見えてきた。
2022-4-16:本文を言われたとおりに修正。図は、もっとわかりやすくなるよう矢印やラベルを加え、図の説明は、本文を参照しなくてもそれだけで図を理解できるものにするよう、もっと詳しく説明せよ、とのこと。今回の修正のメインはこちら。
2022-4-17:図と図の説明の修正。編集長(者)の査読コメントに対する回答書き。カバーレターの作成。修正原稿・査読コメントに対する回答・カバーレターを、英語添削会社Enagoに提出。返却は4/19の15時半。
2022-4-19:水野記念病院から帰宅後、Enagoのサイトから添削された原稿と査読に対する回答ファイルをダウンロード。それを見ながら、提出原稿に修正履歴が残るようにしながら(ASMARの規定)修正を加え、原稿を完成。さらに、査読コメントに対する回答ファイルの添削から修正(添削)履歴を消して、提出用の査読コメントに対する回答ファイルを完成。今夜はASMARに提出する予定ではなかったが(夜に出す手紙はろくなことがないという経験から)、この時点でまだ19時過ぎ。これなら出せそうなので、提出ファイルをASMARのホームページにアップ、提出ファイルの確認のPDFを見たところ、案の定(2022-3-6と同様)、行番号がずれていたので、確認PDFで定まった原稿の行番号を見ながら、改めて査読コメントに対する回答ファイル中の行番号を書き直して再提出。再度確認してもとくに問題なさそうなのでそのまま提出した。今日の提出にかかった時間は1時間半。前回が12時間だったことを考えれば嘘のよう。とりあえず今回でアクセプトお願いします!
2022-4-21:”Current Status”は”Revision Submitted to Journal”。
2022-4-25:編集長からアクセプトのメール。”Current Status”が”Revision Submitted to Journal”だったので、また”With Editor”を経てどれだけかかるのかと思っていたら、いきなりアクセプトが来た。よかった。。
改めて論文日記を見直すと、着手したのはほぼ1年前だ。そのころはまだMendeleyも使っていなかったし、データ解析に2か月もかかっているし、グラフの描き方も知らなかったし、文献の効率的な引用の仕方も知らなかった。
手術のアイディアは斬新で治療成績がよいからすぐにアクセプトされるかと思いきや、そうではなかった。査読では、自分が無意識にスルーしていた論理的な抜けや矛盾を指摘されたり、考察すべきなのにしていないことを指摘されたり、図や図の説明の不親切さを指摘されたり、MCIDやPASSといった新たな統計指標を解析するよう言われたり、など徹底的に指摘されて、ずいぶんと鍛えられた。その意味でArthroscopyの編集者(ASMARと同じ)や査読者の方々には感謝してもしきれない。
2022-5-11:アクセプトのメールに「今の段階ではいつにpublishされるか伝えられない」と書かれてあったので、アクセプトからpublishまでにどのくらいかかっているかASMARの他の論文を調べたところ、だいたい2か月、長いと4か月くらいかかっていた。自分の論文も7-9月になりそう。
2022-5-14:Arthroscopyの編集者からメール。論文を出版社に送りましたと。あとはどのタイミングで出版されるか。
2022-5-23:Elsevierからメール。出版に当たって権利譲渡書にサインしたりなどしてくださいと連絡が来た。さっそく必要事項を記入、オープンアクセス料を支払い、終了。あとは出版を待つのみ。
2022-5-25:Elsevierからオープンアクセス料の領収書のメール。最近Elsevierから領収書ばかり送られてくる笑
2022-6-4:Elsevierから論文の校正に関する通知。48時間以内に校正して論文PDFを返信せよと。本文自体には修正するところがなかったが、利益相反がありになっていたので、それを訂正して返送。原稿が実際に出版される体裁になったのを見ると、いよいよpublishされるのだと実感する。
2022-6-10:Elsevierから「論文がとりあえずインターネットで見られるようになりました」とメール(論文はこちら)。引用の際必要な号や巻、ページ番号などは最終版ができあがってから決まるとのこと。早速見てみたが、訂正を依頼した利益相反ありの部分がPDF版で直っていない!おかげでせっかくの喜びも半減。訂正再依頼も面倒くさいし些細なことなのでまぁいいか。ASMARのサイトで自分の論文の近くにある他の論文を見渡す限り、共著者ゼロは他にないので、その点だけ満足。
自分のキャリアで代表作となりうる論文なので、publishがもっと感慨深いものになるかと思ったが、そんな感慨はみじんもなかった。おそらく、①publishされたことで、この術式は世界中の外科医誰でも行える状態となり、自分の専売特許ではなくなったこと、②評価は他の外科医が行って初めて決まっていくものであるという意味で、この術式はやっとスタート地点に立ったに過ぎないこと、などによるのだろう。
2022-6-16:Elsevierからメール。「ScienceDirectでも論文が見られるようになりました」と。ScienceDirectの中に論文が入ると、研究者からのアクセスがしやすくなるとのこと。
2022-8-15:巻と号が決まった。Arthrosc Sports Med Rehabil 2022;4(4):e1385-e1395. doi: 10.1016/j.asmr.2022.04.027 に。まだPubMedには反映されていないよう。PlumX Metricsによると、現在のところ5人がこの論文をMendelelyに保存したとのこと。
2022-8-28:だいぶ他の論文などが片付いてきたので、ASMARにアクセプトされたときに言われた、Arthroscopy Techniquesへの手術ビデオの提出に着手することに。
2022-8-29:撮影した動画の音声消しをしようとしたが、動画が長すぎてうまくいかない。そこで動画を分割するのを優先すべく、動画を見ながら各手術工程の時間の書き出し。各工程ごとに動画を分割。何も最初に音を消さなくても、分割の際に音を消せばいいだけだった。投稿規定読み。
2022-8-30:どんな感じで論文記事を書けばいいのかわからないので、Arthroscopy Techniquesに掲載されている論文を10数個ダウンロードし、ざっと見。それを見ながら論文ファイルのフォーマット作り。
2022-8-31:Arthroscopy Techniquesの論文を参考にしながら、自分の論文で書くべきことをメモ書き。すでに出た論文がPubMed検索にも引っかかるようになった。
2022-9-1:Arthroscopy Techniquesの文献読み。手術テクニックに関して”Pearls and Pitfalls”の形の表にしている論文が多いが、ここで言う”Pearls”の意味が分からない。onlineのMerrian-Websterを調べても”真珠”としか書いていない。ネットで調べると、けっこうこれを疑問に思っている人も多いよう(Yahoo質問箱にも質問があった)。こういう”裏”の意味がある言い方を学術の場面で使うのはやめてほしいが、そうも言っていられない。考えられるのは、”pearls of wisdom”という言い方の省略形である可能性。そうだとすると、Collins online dictionaryによれば、”お役立ち情報”とか、ときに”明白すぎて退屈に思えること”などと言った意味になる。まぁ英語添削のときに質問しよう。
2022-9-2:投稿規定読み。執筆開始。ついこの間論文にしたばかりだから新たに書くことなどない、と思っていたら、細かい技術的なことでまだ書いていないことが意外と沢山あることに気づく。
2022-9-3:原稿の下書き。細かい技術的なことで書きたいことがたくさんある。こう書いていると、Arthroscopy&ASMARの編集長が、前回論文アクセプト時に「Arthroscopy Techniquesに手術動画&テクニカルノートを出してください」と言ってくれた意味がよくわかる。どうしても最初の論文では、その術式の治療成績などを含めなければならないため、技術的なことのすべてに言及されているわけではない。それゆえ、最初の論文でその術式がどうやら良さそうだということを編集長が認めたら、そのすぐ後に、開発者自身に術式のテクニックについて十分に語り尽くさせるのが、その術式を正しく読者に伝えるのには最も良い方法なのである。術式の開発者にしてみても、後に別の人が自分の開発した術式の治療成績に関する論文を出す際、その人が開発者の意図しない形で手術を行っていて、「この術式はあまりよくありませんでした」などと言われたら、たまったものではない。そういう意味で、開発した術式のテクニックについて語りつくす場を与えてくれるというのは、とてもありがたい話だ。
2022-9-4:原稿の記載(日本語)。今までの経験で得てきたこの術式に関する技術をひたすら書き出す。自分の個人的な経験が学術論文という科学の一部に変換されていく作業なので、これはかなりやりがいを感じる仕事だ。
2022-9-5:方法の英訳。
2022-9-6:イントロダクションの英訳。ディスカッションの段落構成とキーワードの検討。
2022-9-8:ディスカッションの記載。
2022-9-10:ディスカッションの記載。コツと認識していることは日本語に頼る部分が大きい(曖昧で感覚的なことばで認識している)ので、言いたいことが伝わるように英語に直すのが難しい。
2022-9-20:先週はすべての日が忙しかったからか、週末に40℃近い高熱でダウン(コロナは陰性だった)。幸いのどの痛みや咳といった随伴症状はなく、熱も1日で下がったが、昨日の祝日はひたすら体力温存のために何もせず。今朝は1時半に起きたが、体力にまだ不安が残るため、ベッドでぐずぐずして2時に起床。メールを空けてみたら、Journal of Orthopaedic Surgery and Research(JOSR)から査読依頼のメール。確か有名な雑誌だったと思って調べたら間違いない(似た名前のオープンアクセスハゲタカジャーナルということがよくある)。しかも編集長を調べたら、足の外科で有名なMaffulli先生だった。こんなに日常業務が忙しくて、その上査読に対する返答1、足の外科テキストの原稿1、学会発表準備1が重なっているときに来るなんて! とはいえ、ここで断ったらJOSRから査読依頼は二度と来なくなるだろうし、せっかくMaffulli先生に認知されるチャンスを逃すのももったいないし、いつも出しているJournalのImpact Factorと同等かそれ以上のJournalからの査読依頼というのもいいチャンスなので、ここは引き受けることに。確かに忙しいが時間は作ればよい。査読原稿はアキレス腱付着部症に関する論文。今回の査読依頼には確実にこの前ASMARに発表した論文が影響している。
2022-9-21:昨日のJOSRからのメールに引き続き、今日はWorld Journal of Orthopedics (WJO)の編集長からメール。この前のアキレス腱付着部症の論文を踏まえて、解説レビューを書きませんかと。WJOは中国から発行される整形外科のジャーナルの中では最も国際的なジャーナルで、オープンアクセス料が898USDと割安なので注目していた雑誌(Impact Factorもそれなりに高い)。解説レビューなど大御所が書くものだと思っていたら、思わぬ形でチャンスが回ってきた。しかもこの招待を受けて、書いたレビューが一人の査読を通ったら、無料で掲載してくれると。解説レビューはシステマティックレビューと違い、網羅的に書くものではなく、著者が自身の研究結果を踏まえ、新しいアイディアや視点、将来の方向性などに関して独自の見解を述べることができる。このような場を提供してくれるのはとてもありがたい。自分の考えたアキレス腱付着部症手術を全世界に普及させようと目論んでいる身としては、Arthroscopy Techniquesに出そうとしているビデオ論文に加え、とても強力なサポートとなる。受諾が9/29までで、記事の締め切りが12/28。締め切りが12/28なら、今いろいろ山積みになっていることが11月始めでひと段落するので、余裕があるだろう。喜んで承諾。
2022-9-22:WJOの指定されたページに行き、提出予定の記事の仮の題を入力。題を入力する欄の下にアブストラクトを記入する欄もあり、一瞬ぎょっとするが、まぁ適当に書いても後で修正可能だろう。その辺は締め切り間際になって慌てて出す学会抄録で妙に度胸がついている。Google翻訳やGrammaryの助けを借りながら、当たり障りのないアブストラクトを作成して記入。submitのボタンを押すと、よく投稿した後に見る原稿の情報(題名、アブストラクト、提出日、原稿ID、アクセプト日などが細長い表になったもの)が出てきた。表の上に”Invited Manuscripts from Influential Scientists”などと書いてあり、妙に自尊心がくすぐられるが、こうやって結局は編集者の思うつぼになっていることに気づく。これでとりあえずの提出はできたのか?締め切り期日の9/29を待ってみよう。
2022-9-24:JOSRから査読依頼された原稿読み。アキレス腱付着部症に対する踵骨骨切り術の骨切りの方向と角度に関する研究。図形的に考えて当たり前のことを仮説検証している。つまらなすぎて寝そうになった。
2022-9-25:JOSRから査読依頼された原稿読み。原稿はblindになっていないため、著者などが丸わかり。チェコの某大学からの研究だった。Pubmedで調べたら、筆頭著者はこれが2本目の執筆で、原稿チェックをしている共著者2人(contributionsにそう書いてあった)は、1人が5本論文を発表しているのでおそらく直接の指導医、1人が19本書いているのでおそらく教授だろう。大学からの研究を査読する機会はこれで何度目かだが、いつも思うのは、本当に指導医や教授はちゃんとその論文をチェックしているのか、という問題だ。一読しただけで33個もコメントが出てしまう”脇の甘い”論文を大学が提出させてはダメだろう。
ともあれ、8時間かかって計46個のコメントを書き、JOSRに提出…しようと思ったら、提出サイトに”Editorial decision has already been made for this submission and it is no longer available for review.”と出ていて提出できない。もう一人の査読者が早々に”Reject”の査読コメントを出したか?しかし、これはあまりに著者に対して不親切。自分がrejectに遭った時も、もらった査読コメントがどれほど次の提出に役立ったことか。そこで、編集部宛に自分の書いた査読コメントをメールで送って、良い人アピールしておいた。確かにこのくらいの論文でインパクトファクタージャーナルにアクセプトされるのはいかがなものかと思ったが、やはり現実は厳しい。
2022-9-27:編集部からメール。「査読を著者に送りました。また、このやり取りを担当の編集長にも転送しておきます」と。
2022-10-2:解説レビューを依頼されている(2022-9-21)WJOの自分のページにアクセスしたら、まだ原稿を出してもいないのに、論文の “Status” が9月29日付けで “Accepted” になっていた。こんなうれしい話があるなんて。後は原稿を用意するのみ。Arthroscopy Techniquesにビデオ論文を出してそれがAcceptされれば(Atrhroscopy TechniquesはAcceptまでの時間が短い)、ぎりぎりWJOへの論文でもそのビデオ論文を引用できるか(ちょっと時間的に無理か)。とりあえず急ごう。Arthroscopy Techniquesの他の論文を見ながら、ディスカッションで書く内容を検討。
2022-10-3:ビデオ論文を速やかに投稿することに集中。アブストラクトの記載。ディスカッションの記載。全体の手直し。引用文献の選定。残るは図の作成、図の説明、ビデオ作り。
2022-10-4:図の説明。写真の選定。動画のチェック。この前撮影した動画を編集すれば良さそう。
2022-10-5:動画の編集。動画を見ながら切り取る部分をメモ書き、次にその部分を切り取り、つなげてビデオ作成。図の説明の手直し。Arthroscopy Techniquesの投稿規定の確認。他の論文の閲覧。字数の調整。Scribbrで剽窃チェック。前回の自分の論文から剽窃と見なされる箇所が多かった。その箇所に引用文献番号振り。本文についてはひとまず完成。後は図を作って図の説明を調整したのち、Elsevierの英語添削に出し、添削が返ってくるまでにビデオを完成させる予定。病院に研究計画書の提出。
2022-10-6:術前術後のレントゲンやMRIで適切なものを選ぶため、最近さぼっていた手術台帳の記入。
2022-10-7:Elsevierの英語添削に出せるように本文にとりあえずの図を載せる作業。はじめは図を載せずに本文のみを添削に出してしまうことも考えたが、実際に図を本文に載せてみると、本文に細かい修正が次々と出てくるのを実感。やはり図ができてからでないと添削に出してはダメだ。
2022-10-8:手術台帳の記入。今まで手術台帳は日本語と英語/ローマ字を混ぜて記載していたが(統計解析用の表は全部英語/ローマ字でないとバグるので日本語は入れない)、全部英語/ローマ字で入力したほうが圧倒的に速くなることを発見。
2022-10-9:BMJ Openから査読依頼のメール。BMJ?あの有名な?調べて見ると、どうやら本物のBMJ(British Medical Journal)からの査読依頼だった。題名を見ると「最小侵襲手術が外科医の健康に…」といった内容。どうやら、今年出した論文はいずれもキーワードに「最小侵襲手術」と入れていたので、そこで検索されて査読者に選ばれたよう。ただ、あまりに自分の専門分野と異なる内容だし、BMJ Openでは、論文が公開されるのと同時に、査読者の名前と査読内容も同時に公開されるとのことなので、辞退することに。BMJ Openの査読者リストに加えられたとのことだったので、自分のプロフィールのサイトに行き、専門を「Foot and Ankle」にしておいた。これでFoot and Ankle関連の査読が回ってくるかもしれない。
アキレス腱のビデオ論文は、ここ数日中には完成しそうもない。理由は、載せる画像の選択に時間がかかることと、必要な写真の何枚かが足りないことなど。完成は10月下旬になりそう。するとWJOの投稿締め切りまでにpublishされる可能性は限りなく低い。まぁ諦めて完成度の高いものを目指そう。今日も手術台帳の記入。
2022-10-10:手術台帳の記入終了。2021年の手術件数が224件、今年は先週までで200件、アキレス腱付着部症は134件だった。
2022-10-11:論文の手直し。
2022-10-12:本文全体の見直し(図の説明以外)。投稿規定の見直し。動画の切り取りと無音化。
2022-10-25:Monthly Book Orthopaedics(全日本病院出版会)からの執筆依頼の原稿をひとまず提出したので、ふたたびこちらに戻ることに。アキレス腱付着部症に関しては、来週の学会発表、Arthroscopy Techniquesに投稿する予定のビデオ論文、World Journal of Orthopedicsから依頼された解説レビューと、年末に向けて3つ同じネタで発表することが重なっている。ある程度同時進行できるだろう。
今回の学会発表は、あくまでこの術式の布教活動のため。一昨年学会発表したPDFをちょっと手直しすれば済みそう。一昨年のPDFをコピペし、思いついたことを少しずつ追加。
ビデオ論文については、書いた原稿の見直し。ディスカッションが今一つだったので、書く内容の再検討。
2022-10-26:ビデオ論文の図の準備。レントゲンやCTは簡単に準備できるが、術中の内視鏡写真とMRI写真の準備が難しい。その理由は、術中の内視鏡写真はベストショットでなければ使い物にならず、術後MRIは全員の患者さんで撮影しているわけではないことによる。これらを改めて準備するのは大変なので、Elsevierに前の論文で使用した内視鏡写真とMRIの使用許可を申請してみるか。しばらくぶりに論文に戻ったが、論文に関連するストレスは日常生活で最上位のものであることを思い出した。
2022-10-27:図の選定と作成。MRIと内視鏡写真は新たに用意するのをあきらめて、Elsevierに前回の論文の図の使用許可願を提出。ISSN番号を書けとか訳わからない要求に対処しつつ、何とか提出。すぐにElsevierから許可願を受け取りましたとメール。7営業日以内に連絡しますと。
2022-10-28:図の作成。あと一つのところまで来た。昨日の件に関しElsevierからメールがあり、版権は北米関節鏡学会(The Arthroscopy Association of North America, AANA)の方が持っているので、使用許可願はそちらにして下さいと。ASMARのサイトにはElsevierに依頼してくださいと書いてあるが、実は自分たちが版権を持っていたとのこと。だいたいこのようなケースでは、学会事務局の方が企業よりいい加減なので、Elsevierの言う通りだろう。
2022-10-29:残りの一つの図の完成。全体の見直し。
2022-10-30:全体の見直し。大幅に字数をオーバーしたので、その調整。書きたいことを漏らさず書いているかチェックするのは英語では難しいので、自分の書いた論文をgoogleのドキュメント翻訳を使って翻訳。そこで1つ書き漏らしを発見し追加。大丈夫そうなので、Elsevier Language Editing Servicesに提出。5営業日後に返却予定。
この間にビデオのトリミングをしようと思ったが、ビデオのトリミングは、英語の添削が返ってきてからでないとできないことに気づいた。英語ネイティブなら、ビデオを先に作ってから、それに合うように音声を吹き込むことができるだろうが、こちらは、添削してもらった英文を音声にしたのち、それに合わせて映像の長さを調節する、という方法を取らざるを得ない。ということで、トリミングの作業は英語添削が返ってくるまでお預け。
2022-10-31:レビューを依頼された(2022-9-21)World Journal of Orthopedics (WJO) のホームページに行き、投稿規定や利益相反開示フォームなど必要なものをダウンロード。ついでに他の人のレビューを閲覧。皆かなりしっかりと書いている。しかもレビューの一番下に、そのレビューを査読した人の評価がA(excellent)~E(poor)で書いてある!なるほど、著者をレビュー執筆に招待してRejectにはしない代わりに、査読者の評価を出すことによって、「あまり質の低いレビューは出すな」という抑止力としているわけか。これはかなり大変な仕事を引き受けてしまった!ただ、すごくやりがいのある仕事ではある。よくレビューを読んで、「これは勉強になった!」と感動することがあるが、そのようなレビューを書けばいいということだ。
今週に学会があるので、その直前ということで、今日は手術の予定を入れなかった。なので病院で学会準備。一昨年に発表したスライドを一部入れ替えたり治療成績のグラフを入れたりして完成。発表原稿も書いて3,4回練習して終了。5時間くらいで終わった。論文のストレスの高さに比べたらウソのよう。
2022-11-2:Elsevierからビデオ論文の英語添削が終わりましたとメール。さっそくサイトに行って添削されたファイルをダウンロード、添削された部分をチェックしながら提出用のファイルを作成。手術手技の文章を別ファイルにコピペし、それを分割して録音用の原稿を作成。
2022-11-5:録音用の原稿を分割。
2022-11-6:分割した原稿を「音読さん」で音声化。声は足底腱膜炎の動画と同様”Jenny”に設定。それぞれのMP3ファイルに順番、内容、秒数をタイトル名をつけて保存。セリフと間の秒数を足して、作成すべきビデオの長さを計算。Wondows標準ソフトのフォトでビデオをトリミングしながら音声ファイルをそこに載せていき、各場面ごとにビデオを作成。半分終わった。
2022-11-7:残りのビデオを作成。全部つなげて完成、と思いきや、自宅のパソコンが非力で、全部の動画をつなげてエクスポートするときに止まってしまう。仕方ないので病院のパソコンで打ち出すことに。病院でエクスポートしてみたら、高解像度では200MBを超えていた。投稿規定は100MB以下なので、低解像度(79MB)でエクスポート(そこまでひどい劣化を感じなかった)。カバーレター、タイトルページ、原稿、図、利益相反開示フォーム、ビデオなどの必要なファイルを整えて、Arthroscopy Techniquesに提出。論文中で転載した図の転載許可証を、まだ北米関節鏡学会(the Arthroscopy Association of North America, AANA)からもらっていないが、それは後付けでも何とかなると居直る。ていうか論文の提出先がAANAなのだから、そこらへん気を利かせて「転載の件は処理しておきました」とはしてくれないものか(たぶん無理)。
2022-11-8:ビデオ論文も査読が来るまで時間があるし、強剛母趾も英語添削待ちなので、年末締め切りのアキレス腱付着部症のレビュー論文に着手。これまで他の人のアキレス腱付着部症のレビューをたくさん読んでまとめていくつもりでいたが、いくら読んでも自分の論文作業はまったく進んだ感じがしないので、その作戦は止めた。人のまとめから自分のまとめを引き出すのではなく、自分は自分でまとめるべきだ。まずは4月に出した論文のときにまとめた文献の表の見直し。
ビデオ論文のほうの”Current Status”は”Submitted to Journal”。
2022-11-9:文献のまとめの表への追加、各論文の売りを明記。
ビデオ論文のほうは”Current Status”が”With Editor”に。
2022-11-10:今日もPubMedでアキレス腱付着部症の論文の検索。その途中で見覚えのある題名の論文を見かけ、確認したところ、2022-9-25にJOSRから依頼されて自分が査読した論文だった。結局はその査読を提出する前にEditorがDecisionをしてしまったのだが、その結果はrejectではなくてなんとacceptだった!それぞれのサブセクションに分けて書くべき記述の混乱や、統計処理の方法とその結果の解釈の間違い、不適切な図の示し方、など至る所が不備だらけだったので(46個もコメントが出た)、「このクオリティなら一発rejectでも仕方がない」と思っていたが。。一般にアメリカのジャーナルの方がヨーロッパのジャーナル(JOSRはヨーロッパ)より口うるさいが、いつもアメリカのジャーナルで大量の厳しい査読コメントに痛めつけられている身としては、こんないい加減な論文が通ってしまうことに軽くショックを覚えた。ただ、ノーベル賞を見ても、アメリカが毎年大量に輩出し、ヨーロッパが束になってもアメリカに勝てない現状を見ると、論文に対する姿勢としては、アメリカのジャーナルの方が正しいのだと思う。自分は今後どうするか。やはりアメリカのジャーナルにしよう。
2022-11-11:アキレス腱付着部症の論文を調べていると、JOSRの編集長のMaffulli先生も、その自分の査読した論文の術式(踵骨骨切り術)に関する論文を多数出していることがわかった。おそらく興味のある内容の論文だったので、よく吟味することなくacceptを即決したのだろう。
2022-11-13:検索・ダウンロードした論文読み。全部を丁寧に読む時間はない。ざっと見て自分のレビューに生かせそうな箇所をメモ書き。
2022-11-14:検索・ダウンロードした論文読み。
2022-11-16:過去のレビュー文献を見ればどれもクオリティが高いし、アキレス腱付着部症の文献を調べれば調べるほど膨大な文献が出てきてしまう。これはどうも方向転換しないと始末に負えない。WJOから求められたレビューは何かを改めて確認すると、招待メールの中に、「我々はあなたに『解説タイプのレビュー(commentary review)』を書くことを希望します。その中では、あなたの最新の研究結果に基づいて、新しいアイデア、新しい視点、新しい方向性を提案し、この分野の現在の進歩と将来の方向性について議論することができます。このような解説記事は、読者や研究者への一般的なガイドとして機能し、この分野の発展の方向性を導きます。」と書かれてあった。すなわち、過去を振り返るレビューではなく、自分の論文で示した新しい術式の発想を出発点とした解説記事を書けばいいのだった。これなら何とかなりそうだ。自分の論文の中で示した「骨棘を削ることによって内視鏡のためのワーキングスペースを作る」という発想が、従来にはない発想だったので、その発想と他の最小侵襲手術の発想との比較や、その発想が応用できそうな疾患(これはすでに自分が行っている手術も含まれるが)とその疾患の現在の術式との比較などについて述べればよさそうだ。他の人と似たり寄ったりのレビューでなく、自分にしか書けないレビューを書こう。
2022-11-17:昨日の考えから最小侵襲手術のレビューなどを集めて読んでみるも、内容が広くなった分、さらに始末に負えない感じとなった。これなら今まで文献集めしていたアキレス腱付着部症のレビューの方がまだましだ。そもそもレビューを書こうとするのに、文献検索を面倒だと思うのはダメだろう。レビューなのに文献をあまり上げていないものはレビューですらない。たくさんの文献に当たらなければならないのは仕方ないと諦めて、他の著者に負けないレビューを書こう。
査読待ちのビデオ論文の方は、”With Editor”のまま。
2022-11-18:文献読み。Mendeleyにストックした大量の論文を、まずはレビューかケースシリーズか比較試験か実験かを区別し、ケースシリーズは人数、比較試験と実験は要旨を簡潔にメモ。簡潔にメモするには、ひらがなをすべて抜いて漢字だけを並べると便利。中国語はすばらしいと実感。レビューは構成だけを見ておいて、後からGoogle翻訳を使って全体をざっと読む予定。
2022-11-19:Mendeley内の文献の整理。重複したものを削除したり、入手していないものを入手したり。
2022-11-20:Mendeley内の文献の整理。ひとつの文献を除いてすべて入手し、そのひとつは文献複写サービスに注文。すべての文献に前々日に書いたようなタグ付け。だいぶ見やすくなった。
こんな作業をなんだかんだ一日中やっていると、大学生のときにやっていた数学の塾講師バイトを思い出す。当時、数学の参考書や問題集を130冊持っていたが、それらすべてに目を通し、良問をピックアップ、パターン別(数ⅠAから数Ⅲ全部で110パターン)に易から難に並べ替え、初めて学んでもいきなり難問が解けるようになるような問題集作りに全力を傾けていた。そのときはただ夢中で作っていたが、今になって文献のまとめに生かされるとは思ってもみなかった。
2022-11-21:レビュー文献読み。レビューだけで30本もある。何をまとめているかの整理。
2022-11-22:レビュー文献をGoogle翻訳。ドキュメントの翻訳機能を使用。
2022-11-24:ひたすらに文献読み。レビューを全部Google翻訳したが、変な日本語で読んでも英語で読んでも大した差がないので全部破棄。徹底的に英語で読み続けるほうが潔い。
2022-11-25:ひたすら文献読み。いくら読んでも自分の論文が進んでいるわけではないし、自分の論文の形もまだ見えてこないので、プレッシャーでおなかが痛くなる。
Arthroscopy Techniquesで査読中のビデオ論文は、”Current Status”が”Decision in Process”に。
2022-11-27:ひたすら文献を読み続けていくことで自分の論文が自然と出来上がることは決してないので、方向転換することに。①自分の論文のアウトラインを決める、②そのアウトラインに沿って必要な文献を集める、③日本語で書く、ようにしてみよう。何しろこの解説的レビューでは、アキレス腱付着部症全般を網羅するのではなく、最近の動向を踏まえ、将来の治療や研究の方向性を示すようなものを書けばよいのだ。
この方法に変えてみたら、少なくとも今日は順調に進んだ。アウトラインに沿って集めた文献をReferencesに並べると、似ていながらも少しずつ違う題名を見比べることによって、それぞれだいたいどんなことが書かれているか分かるようになり、自分の書きたいことも明確になってくる。何しろ文献をReferencesに書くのでさえ、おそらく100本以上の論文を引用するとなれば一苦労だ。それが少しずつでも進むので、精神衛生上にもよい。
2022-11-28:とにかく論文数が多いので、それらを一望に把握するのがとても困難。そこで、Mendeley内の文献を、AbstractだけGoogle翻訳して日本語にしたら、全体を把握する時間がずいぶんと減った。
2022-11-29:publishされたアキレス腱付着部症内視鏡の論文を書くときに作った文献のまとめのExcelの表に、今回レビューを書くにあたって集めた文献を追加する作業。結局これが自分の中で一番しっくりくる。ただ、昨日Mendeley内に保管した文献をAbstractだけ日本語訳したが、これはExcelの表を作るのにもとても役に立った。昨日今日でだいぶ書けそうな気になってきた。
2022-11-30:Excelの表に手持ちの文献をすべて記入。全部で136文献もあった。どうりで把握しにくいわけだ。もう一度各文献のAbstractを読み、どれを採用してまとめるかを吟味。
2022-12-1:Mendeleyにため込んだ文献を見ながらひたすらにExcelの表に内容を記入。文献を見る際、Abstractは読むが、本文は術式の詳細などの確認程度。むしろReferencesを見て、網羅し損なっていた文献の後拾遺。その結果、文献はさらに多くなり、160を超えてきた。やるからには徹底してやりたい。WJOから締め切りが12月28日であるリマインドメールが届く。
2022-12-2:ひたすらにMendeleyにため込んだ文献のAbstractを読み、本文にざっと目を通してExcelに要点をまとめ、Referencesを見て網羅し損なった文献を入手し、Mendeleyに入れる作業。やっと3割くらい終了したが、文献が195にまで膨らんでしまった。
2022-12-3:昨日と同じ作業。読んでも読んでもさらに論文が増える。214にまで膨らんだ。いい論文は他で引用されていないようないい論文を引用していることが多く、文献検索能力も高いことがうかがい知れる。
2022-12-4:ひたすらにMendeleyにため込んだ文献の要点をExcelに記入。これ以上文献を増やしたからと言って、自分の論文の出来を大きく左右するわけではないので、新たな文献探しはやめた。むしろ今手元にある文献をしっかりと吟味した方がいいだろう。一日中やって全体の5分の3程度終了。
2022-12-5:ひたすらにMendeleyにため込んだ文献の要点をExcelに記入。明後日までには終わらせて、本文作成に移りたい。
2022-12-6:ひたすらにMendeleyにため込んだ文献の要点をExcelに記入。あと20本くらい。今日中に終わるか?
それにしても提出中のビデオ論文が”Decision in Process”のまま動かずで気味が悪い。
2022-12-7:昨日終わりそうだったが、外勤先の水野記念病院にパソコンを持って行くのを忘れてしまい、昼休みに作業できず。午後は過去最高に混んでいたので、仕事から帰宅後も疲れてできず。気を取り直して今日残り20本の文献のまとめ。終了。一通り把握できた。まずはできあがったExcelの表を見ながら、それぞれの文献をどのサブセクションで利用するか色分け。あっさり色分けできるものから、どう利用したらいいものか決めかねるものまである。何度も表を見ながらひたすら色分け。
2022-12-8:サブセクションに対応して色分けした文献を色ごとに整理。まだ色がついていない文献はもう一度見て色を決定。全体振り分けた。次に、各サブセクションごとに、文献をどの順番で引用していくか検討。
2022-12-9:各サブセクションごとに、文献をどの順番でどう引用していくか検討。しかし、従来の標準的な術式(大きな皮切、骨棘切除、アキレス腱付着部を切り離し、内側の骨削り、付着部の再接着もしくは腱移行)についてレビューし始めると、いくら書いても書ききれないし、このレビューは最小侵襲手術についてであることがぼやける。そこで従来の術式についてのレビューはばっさり切ることに。その上で原稿執筆開始。なんだか書けそうな気になってきた。
2022-12-10:各サブセクションごとに、引用すべき文献を日本語で簡潔な2⁻3文にまとめて原稿に記載。文献を見た上でまとめるので、1文献当たり結構時間がかかる。ただ、この作業をひたすら繰り返せば論文完成は近づいてくる。目一杯に時間を投入するのみ。
2022-12-11:各サブセクションごとに、引用すべき文献を日本語で簡潔な2⁻3文にまとめて原稿に記載。だいぶできあがってきた。
2022-12-12:ほぼ全体書きあがったので、より正確に引用内容を記載しなおし、Google翻訳でまともな英語になるように校正。投稿規定の確認。
2022-12-13:投稿規定に定められた項目を原稿に記入。各サブセクションのGoogle翻訳。翻訳した英語でおかしなところの修正。
2022-12-14:各サブセクションのGoogle翻訳。翻訳した英語でおかしなところの修正。文献欄の記載と本文中に文献番号の記入。少しずつ英語論文に変わってきた。
2022-12-15:ひとまず本文は完成。残すは図の作成、図の説明と全体の見直し。書く内容に即したものに文献を絞ったら、結局90個だけになった。病院で画像を新たに用意し、Illustatorで矢印を記入したりなどの加工。図の説明も書いて完成。明日の朝に全体をチェックした上で、英語添削に出す予定。
2022-12-16:全体のチェック。まずは原稿をGoogle翻訳して、おかしな日本語になっていないかチェック。素直な日本語になっていないところは、だいたいおかしな英語のことが多い。その後、全体を英語で通読し、単語など変えるべきところがないかチェック。大丈夫そうなので、剽窃はScribbrのサイトでチェック。2000円程度でお得。図の説明のところに自分のもとの論文と似た記載が多かったので、そこに引用文献番号を記入。最後にElsevier Language Editing Servicesに提出。添削の返却が12月22日予定。
今回のレビュー論文作成を反省すると、漠然と他のレビューを読んだり、文献を集めたりしたのが無駄だった。良かったことをマニュアル化すると、①書きたいレビューの構成を決める、②各構成ごとに論文を集める、その論文から孫引きをして漏れがないようにする。③Excelの表に各論文の内容をまとめる。その際、集めた論文をMendeley管理にして、Abstractだけ日本語訳にしておくと早い。④各構成ごとに、集めた論文をどの順番で引用するか考える。⑤引用すべき論文を2,3文に簡潔にまとめた文を原稿に記載していく。⑥それらの文を整えて日本語論文を完成させる。⑦英語に翻訳する。という感じか。英語でいきなり書ければいいが、論文は100%の知恵を振り絞って考察しなければならないので、とても英語でそのレベルの思考をするのは無理。なので自分的には日本語でまずまとめなければならない。
2022-12-17:ここ1カ月間、レビュー論文のために毎日1-3時起きだったが、今朝は気が抜けて6時起き。久しぶりに朝寝坊した。ビデオ論文の方は以前”Decision in Process”のまま。どうした?
2022-12-23:Elsevierから英語添削の返却。今回はReferencesが90もあったためか、期日ちょうどの返却だった。今回の添削で目についたのは、キーワードが大幅に直されていて、それはWJOの投稿規定によると、キーワードはPubMedのMedical Subject Headings(MeSH)ツリーから選択するようにと書いてあったかららしい。前回アクセプトされたアキレス腱付着部症の論文でも、せっかくキーワードに色々とたくさんの単語を入れたのに、それがPubMed検索で生かされない(自分の論文がうまくヒットされない)のを疑問に思っていたが、なるほどMeSHツリー内にある単語でないと検索に生かされないということか。文全体を読み直すと、添削としては問題ないが、細かいところで修正すべき点が意外とある。まだ期日に余裕があるので、今日は見直しに徹して明日提出しよう。
2022-12-24:今日は有給休暇。何か用事があって休みにしたのではなく、今日の外来予約が1か月前まで0だったので、そのまま休んでしまうことにした。WJOにレビュー論文の提出。初めてのジャーナルなので入力に不慣れな点もあったが、割とシンプルな構成なのでよかった。最後に「提出に成功しました」と表示されたが、その後にWJO内の自分のLog Inページに行っても、提出が反映されていないので、若干の不安が残る。
2022-12-29:ビデオ論文についてArthroscopy Techniquesの編集長からメール。いくつかの改訂すべき点を改訂すればアクセプトしますと。”Your manuscript is provisionally acceptable.” 30日以内に返送とのこと。見ると、「時制を変えろ」とか「この表現は削れ」など。元気が出る。
若干提出されているか不安だったWJOも自分のページを見てみると、ちゃんと査読が始まっていた。
2023-1-4:年末年始はどうしてもビデオ論文の修正をやりたくなかったが、その理由は、病院のパソコンでないとビデオの修正ができないことにあったようだ(今日病院に出勤したら、急にやる気になっていた)。改めて編集長からのメールを見ると「おめでとうございます」と書いてある。ただ直せばいいだけだ。早速メール内にあるコメントをコピペし、修正の開始。
2023-1-5:論文の修正。時制を直したり、文献を差し替えたりなど、大したことない作業だが、間違いがあってはならないので結構疲れる。コメントへの返答、カバーレターなども含め4-5時間で終わらせて、Elsevierの英語添削に提出。
続いて動画の編集。編集長のコメントの中に、「動画の中に個人情報が見えるのでそこを塗りつぶせ」の指示。たかが動画の一部を消すだけなのに、それほど簡単にはできない。いくつかの無料動画ソフトをダウンロードしてきて、一番編集が簡単と思われたEaseUSというソフトだけを残し、残りはアンインストール。EaseUSは、Windowsの標準搭載動画編集ソフト「フォト」に、いくつかのボタンが加わっているだけのようなシンプルさ。そのボタンの一つに「モザイク」があり、それをクリックすると動画内に”切り取り”のような枠が出て、モザイクをかけたい部分に合わせ、解像度を調整、エクスポートしたらおしまい。あとはElsevierから添削が返ってきたら、添削された手術説明の文を細切れにして「音読さん」で音声ファイル化し、今日作ったモザイク入り動画に載せてつなげれば完成。来週中にはArthroscoy Techiniquesに提出できそうだ。
2023-1-11:Elsevierから英語添削の返却。今回は過去形を現在形にするような原稿の修正に対する英語添削だったので、直されたところはほとんどなかった。早速それを見ながら、提出用の原稿とカバ―レター&査読コメントに対する返答のファイルを作成。「音読さん」で動画のナレーションファイルの作り直し。
この前作ったモザイク入りの動画を見たら、動画内にロゴマークが現れていた。無料お試し期間が過ぎたために出てきたらしい。他のソフトを検索してみると、ロゴマークの入らない無料動画ソフトもあるようだが、いずれにせよ機能に制限がかかってわずらわしいはずなので、そのままEaseUSを購入することに。その上で動画の作り直し。
2023-1-12:昨日のうちに動画は作成したので、今朝提出することに。Arthroscoy Techiniquesのサイトに行き、動画や訂正した原稿、査読に対するコメントファイルなどをアップロード。最終確認のPDFで提出物を確認すると、例によって行番号がずれているので、それを見ながら改めて査読に対するコメント内の行番号を修正し、提出。
2023-1-13:”Current Status”は”Revision Submitted to Journal”。
2023-1-29:あいかわらずArthroscoy Techiniquesの”Current Status”は”Revision Submitted to Journal”。
2022-9-20にも書いたJournal of Orthopaedic Surgery and Research(JOSR)の編集長のMaffulli先生からメール。「私はあなたをJOSRの論文の査読に招待します」と。結局は査読依頼なのだが、「招待」とは物は言いよう。前回の査読のときは、Maffulli先生が独断でアクセプトにしてしまったため、自分の書いた46個の査読コメントは生かされなかったが、その努力が認められたのか、また査読依頼が来た。断る理由もないので承諾。今回は中国の医科大学からの外反母趾に関する論文。締め切りは2月8日。
2023-2-5:査読作業。とてもよく書けている。①ディスカッショ内にイントロダクションで書くべき内容が混在している、②他の研究との比較が少なすぎる、③目的と結論が対応していない、が目につくくらい。
2023-2-6:昨日に引き続き査読作業。ざっと見はよかったが、細かくチェックしながら査読コメントを書いていくと、果てしなく指摘したい点が出てくる。検定法の記述がいい加減、小数点以下の桁数がそろっていない、本文と表の数値が合っていない、など。こういう細かいところは、論文を提出する前に自分でチェックしてほしい。それと、ディスカッションで一般的な事柄をダラダラ書く論文が多すぎる。ディスカッションは、まず自分の研究結果を簡潔にまとめたのち、別の研究結果と比較しながら自分の結果について考察、最後にリミテーションを書く、とおおまかに型が決まっている。
2023-2-7:査読コメントの英訳。JOSRに提出。
2023-2-12:Arthroscopy Techniquesの編集長からアクセプトのメール。とりあえずめでたい。
2023-2-16:アメリカ・デンバーの理学療法士さんから、内視鏡手術のリハビリに関する質問のメールをいただいた。その方は今アキレス腱付着部症の術後リハビリに関する本を書いているとのこと。自分の内視鏡手術が広まるよいチャンスなので、喜んで回答のメール。
2023-3-1:Arthroscopy Techiniquesから「原稿を出版社に送りました」のメール。Arthroscopy Techiniquesに載っている他の論文を見たら、だいたいアクセプトから出版までに2カ月半くらいかかっていたので、出版は4月後半と思っていたが、予想より早く出版されそう。他の論文を見た際、日本人では誰の論文が出ているか探したところ、直近に知り合いの所沢中央病院の上村先生の膝関節鏡論文が載っていた。
2023-3-3:Elsevierからメール。権利に関するフォームの記入をして下さいと。指定されたサイトに行き、権利譲渡書やオープンアクセス料支払いなどを完了。あとはElsevierからの最終校正原稿が来るのを待つばかりだ。
2023-3-8:2023-1-29から査読していた中国の先生の外反母趾の論文に関して、JOSR編集長のMaffulli先生からメール。「校正原稿が送られてきましたので再査読お願いします」と。承諾してさっそく原稿を見ると、どこもちゃんと直されている(28個のコメントすべて「~して下さい」と、修正の方向性を示しておいたが)。こちらが指摘したとおりに修正したら、それ以上に文句のつけようがない。明日もう一度見直して「満足のいく校正です」と返事しよう。
2023-3-13:JOSRから依頼された再査読。本文の中で一カ所ひどいミスをしていたので、その部分の指摘。それ以外はほとんど修正しなくてよいかと。一方、アブストラクトはお粗末さが目立つ。文が冗長なため、記載すべき結果が省略されてしまっている。どうして文を簡潔にして、必要な要素を漏れなく盛り込もうとしないのだろう。
2023-3-15:JOSRから依頼された再査読。アブストラクトを直しさえすればアクセプトでもよい出来だから、「以下の文を参考にして、必要な情報がすべて含まれるようにして書き換えて下さい」と、またこちらで書いてあげることにした。あちらだって早くアクセプトしてほしいだろうし、こちらだっていつまでも査読にかかわるのも面倒だ。終了し提出。
2023-3-18:Elsevierからメール。出版用の校正原稿が出来上がりましたのでチェックしてくださいと。早速校正原稿をダウンロードしてチェック。
2023-3-19:校正原稿のチェック。特に直すところもないので、校正原稿のPDF内のいくつかの質問項目を記入した上、メールで返送。「48時間以内に返送のこと」と来たメールに書かれてあったのを見逃していて一瞬ヒヤッとしたが間に合った。
2023-3-21:JOSRからまたメール。査読している論文の修正が終わったのでまた査読してくださいと。見ると、言われた通りには直しているのだが、その修正によってアブストラクトの制限語数(350語)を30語以上もオーバーしている。修正をしながらも投稿規定は死守するというのは当たり前だと思うのだが、そういうことも言われなければ分からないのだろうか。
2023-3-24:アキレス腱付着部症最小侵襲手術に関するレビュー論文は、やっと一人の査読が終わったらしい。その人は一発アクセプトの評価だった。二人の査読が終わったらpublishに向けて進むようだが、進行状況を見るかぎり、査読者が中々つかないようだ。
2023-3-25:JOSRから依頼の査読。アブストラクトの語数調整だけすればよいので、削るべき部分をこちらで指示。その上で「マイナーリビジョンののち再査読なしでアクセプトでよいと思います」と編集長にコメントして提出。
2023-3-28:Elsevierからメール。「校正原稿のチェックがまだ送られてきていません」。3/19に送ったはずなのに届いていないと。なぜそんなことが起きるのかと思ってチェックすると、こちらへの送信はElsevierの校正原稿チェック依頼用の共通メールアドレスから発送しておきながら、そのメールにCCとして担当者個人のメールアドレスがあり、返信はそちらに送ってほしかったよう。そんなのわかるか! だったら「このメールに返信してください」と書かずに「CCにある担当者メールアドレスに送って下さい」と書くべきだ。担当者個人のメールアドレスに改めて返信。
2023-4-2:2022-12-24にWorld Journal of Orthopedics (WJO)に提出していたアキレス腱付着部症の最小侵襲手術のレビュー論文の進行状況が、”Send to Company Editor-in-Chief for First Decision”に変わった。
2023-4-13:WJOの自分の論文の査読状況を示すサイトに行ったところ、”Potential Acceptance”とあり、編集長からRevisionコメントが書かれてあった。内容に関するRevisionはなく、図は編集可能なようにパワーポイントで提出せよとか、図の下に著作権情報を入れよとか、表のラインは一番上と一番下のラインと列のラインだけ残して後は全部非表示にせよ、などの指示。慣れない雑誌だとこういう点を指摘されただけでもどきどきするが、とりあえずはめでたいようだ。
2023-4-14:図をパワーポイントで作り直し。数年前の学会発表までIllustatorを使わずパワーポイントで図を作っていたのでお安い御用だ。
2023-1-29から査読していた論文に関してJOSRからメール。アクセプトされましたと。
2023-4-15:WJOのrevision。表の余計な線を消した修正原稿ファイルと図用のパワーポイントを提出しようとするも、どこに提出したらよいのか分からない。仕方ないので、ヘルプデスク宛に「提出の仕方が分かりません」のメールを書き、これらのファイルを添付することにした。ちゃんと処理してくれるか?
2023-4-16:WJOの自分のページに行って再度提出法を探すもわからず。普通なら自分の提出中の論文のところにrevisionなるボタンがあって、そこを押すと提出の手続きに移るはずだが、そのようなボタンが見当たらず、”new submission”くらいしかない。まぁ昨日メールしたヘルプデスクからの返事を待とう。
2023-4-17:WJOの自分の論文の欄にHandleなるボタンがあると指摘され、そのボタンを押すと、reviseとdeclineのボタンが表示された。ここからrevision fileを提出できそうだ。言われるがままに入力していくが、単にファイルをアップロードするのではなく、イントロダクションや結論、文献などを別々に入力しなければならない。特に文献など、コンピュータで認識される引用と異なると訂正を要求される面倒さ。最後にファイルをアップロードしたのち、submissionを押そうとするも、必要なファイルをアップロードされていないと認識される。そもそもメールによるrevision (potential accept)の連絡すらない、revisionの開始ボタンが分かりにくい、文献のちょっとした書き直しをしつこくさせられる、revisionで必要な提出ファイルについて説明しているサイトがない、など、システムのあらゆる点に不備があり、怒りが爆発しそうになる。
改めてWJOサイト内の自分のページに行き、色々見ると、自分の論文情報の書かれている小さな表の中にメールのマークがあり、それを押すと、自分に送ったことになっているメールが出てきた。そのうちの一番最新のものを開けると、その中にRevisionの手続きなどが詳しく書かれていた。こちらのメールアドレスを知っているのだから、こういう重要な事はそのアドレスに送るべきだろう。WJOのサイト内に通知情報をとどめていたのでは、著者がわざわざサイトにアクセスしないと認知できない。3カ月以上も査読にかかっておいて著者にDecisionメールも出さず、自分からサイトにアクセスして気づけというのか。バカにしているにも程がある。
ともあれ、とりあえずその通知を見ながら修正すべきところは修正し、再提出をしようとするも、最後に「必要なファイルを最初にアップロードしてください」と表示されるのはあいかわらず。まだピットフォールがあるようだ。提出期限は27日までなので、その間に解決しよう。
2023-4-18:今朝も考えられるあらゆる手段を講じながらファイルアップロードに取組むも提出できず。こんなことを10時間近くもやっているのにできないのは、システムの不備としか言いようがない。
2023-4-19:今朝も引き続き最終提出のトライ。Conflict of InterestのPDFファイル(WJOサイトからダウンロードしたもの)がアップロード時に正しく表示されないので、PDFの形式を色々変えるもやはりうまく表示されず。仕方ないのでPDFからWordに変換してアップロードしたら正しく表示された。それはいいとして、考えられる限りのあらゆる手段を尽くすもやはり提出が完了しない(もう13時間くらいトライしている)。ヘルプデスクに4月15日に出した「提出の仕方がわかりません」のメールに対する返事が来たので、渡りに舟とばかりに、「必要なファイルはすべてアップロードし終わり、最後に『提出』ボタンを押すのに、なぜ提出が完了しないのか」の質問メールを返信。とりあえず提出を完了したい意思は伝えることができたので、このまま提出期限(4月27日)が来ても、期限切れRejectになることはないだろう。
2023-4-24:なかなかWJOのヘルプデスクに出したメールの返信が来ないので、もう一度WJOのサイトにあるヘルプデスク宛てのフォームを使って提出が完了しない旨のメールを提出。「今アップロードしているファイルのまま提出を完了したいのにできない」と、提出の意思を明示した。
2023-4-27:もう一度WJOのサイトにアクセス。今日が提出期限の日。提出の最終ステップの”ファイルをアップロード”ページに行くと、自分のアップロードしたファイルの先頭に、元の原稿ファイルがいつの間にか現れていた。今回のレビュー論文は基本的にRevisionなしのアクセプトだったので、ほとんどそのままでよいのだが、査読者にキーワードに関して指摘されて2つ追加したこともあって、初めてファイルをアップロードする際、この元の原稿ファイルを削除した上、再アップロードしようとしたところ、それができないようなシステムになっていた。どうやらこのファイルを消すと不完全な提出と見なされるよう。ファイルの横にはEditとDeleteのボタンがあるのだが、するとEditの一択しかないということか。しかし他のファイルでEditを押したところフリーズしたので、おそらくEditを押して元の原稿ファイルにキーワードを追加しようなどとすると、またトラブルになるだろう。”Submit”を押すと、昨日までは反応しなかったものの、今日は反応する。元の原稿ファイルを下手にいじくると、せっかく有効になっているSubmitボタンがまた無効になる可能性が高いので、そのままSubmitを押してしまうことに。この際、細かいことは言っていられない。これでめでたく提出。まったく綱渡りもいいところだ。
2023-4-29:WJOからアクセプトのメール。あとは著作権使用許諾契約書にサインしてくださいと。指定されたサイトに行き、acceptを押しておしまい。何だか査読が進まずに悶々としていたが、結局Revisionなしのアクセプトだった。とりあえずはめでたい。
2023-5-9:Arthroscopy Techniquesからメール。論文がpublishされましたと(こちら)。とりあえずめでたい。
WJOからメール。最終的なアクセプトとなりましたと。まだ最終的ではなかったのか!WJOのサイト内の自分のページに行くと、5月6日に何やらメールが届いている。見ると、「校正原稿が出来上がりましたので、48時間以内にチェックして送り返してください」と。どうしてこういう大切なメールをこちらのメールアドレス宛に送らずに、WJOのサイトのマイページ内のメールボックスにとどめておくのか?そんなに毎日毎日WJOのサイト内の自分のページにアクセスするわけないだろう!そうか、48時間経過したから、それをもって締め切りとし、最終アクセプトメールを送ってきたのか。間に合うかどうかは分からないが、校正原稿をチェックして返送することに。見ると大した間違えはないが、八潮がYahioになっている。まぁ別にいいや。
2023-5-10:WJOの編集者からメール。修正を受け取りましたと。これで所属がYahio病院にならなくて済んだ。
2023-5-27:Foot & Ankle Specialist(FAS)からレビューの依頼。Haglund症候群に関するもの。Haglund症候群とアキレス腱付着部症の関係は色々と議論のあるところだが(アキレス腱付着部症のレントゲン論文はそれをネタにしている)、Haglund症候群のレビュー依頼も、おそらく最近出したアキレス腱付着部症の論文が関係しているだろう。人が一生懸命書いた論文をレビューするのは大好きなので快諾。
2023‐5‐30:WJOからメール。校正原稿が出来上がりましたのでチェックして48時間以内に返送してくださいと。見ると所属がYahioのまま変わっていない!もう一度修正依頼。まぁこの論文の読者にとってはYahioだろうがYashioだろうがどうでもいいが。
2023-6-7:ここ数日間2時に目が覚める日が続いていたので、昨日は缶ビールを半缶飲んでから寝たところ、今日は3時半に起床。2時は早すぎて調子がくずれてくるので、この3時半がベスト。ベストの時間に起きるとやる気も上がる。先日FASから依頼を受けた査読を開始。割とちゃんとした論文だと思ったら、足の外科内視鏡手術で有名なTH Lui先生のグループからの論文だった。
北京大学の先生から突然のメール。何事かと思ったら、その彼はハーバード大学の大学院に留学中とのことで、アメリカで研究者としての永住ビザを取るために、彼の科学的貢献を評価する専門家としての推薦者になってくださいと。何でこちらが推薦者なのかというと、アキレス腱付着部症内視鏡手術の論文で引用したある文献の共著者の一人にその彼が含まれているとのことで、こちらがその論文を引用したがゆえに、その彼の科学的貢献を評価しうる推薦者になることができるとのこと。しかも、推薦者の条件は、「知り合いでないこと」と「一緒に働いたことがないこと」とのことで、まさに合致するとのことだった。そんな関わりで推薦者をお願いする次第なので、その論文を引用してくれて大変感謝しておりますとも書いていた。いきなりお礼を言われてこちらもびっくりだが、文面から彼の必死さも伝わってくるので引き受けることに。北京大学からハーバードに留学しているエリートの推薦者が自分でいいのか?笑
2023-6-8:FASの査読の続き。
昨日の北京大学の先生からメール。ありがとうございますと。推薦状に関しては弁護士さんと相談しながら原稿を作ってお送りしますので、チェックしてよければサインをくださいと。感心するのは、メールの文章がとても丁寧。こちらなどは英語が下手だから、意志くらいは伝えられるものの、日本語の敬語にあたるような丁重な表現など全くできないが、そういう表現も完璧に身につけている。しかし、英語ができることと歴史に残る業績を上げられることとは別問題、などと妙な開き直りを見せる。
国際足の外科学会(International Federation of Foot & Ankle Societies; IFFAS)の日本での委員をやっている東大の張(ちゃん)先生からメール。IFFAS前理事長の田中康仁奈良医大教授から、来年のIFFASのシンポジストを推薦してくれとメールがあったとのことで、こちらのことを推薦したいのですがいいですか、という内容。来年5月でソウルで開催とのことだが、1年あったら英語での発表の準備もできそうだし、性格のいい後輩の張先生からの依頼を無下に断るのも悪いので、引き受けることに。アキレス腱付着部症の内視鏡手術を世界中に拡散しようと企んでいるので、うまく利用しよう。
2023-6-9:昨日IFFASのシンポジストを引き受けてしまったが、シンポジウムなので、発表するだけでなく、その場で討議などをしなければならない。今はまったくそんな英語力がないが、この1年でどう準備していくか。そういえば、Googleの日本のCEOがどこかで「今でも英語は話せない。いろいろなネタ話を100個くらい用意して丸暗記しておき、会話では強引にその用意しておいた話に持って行く」と言っていた。今さら当意即妙な英会話能力など身に付くわけがないのだから、この方法が一番いいだろう。まずは自分の書いた英語論文を丸暗記しておき、あとは予想される質問に対する答えを準備して、それも丸暗記しておこう。リスニングは、自分の英語論文を”音読さん”で音声化しておき、2倍速で聴きとる練習でもしておこうか。とりあえず毎日やろう。
さっそく自分の英語論文を朗読。英語の朗読など何十年ぶりだ。口が全然回らない笑
FASから依頼された査読。6月15日提出期限。
2023-6-10:昨日WJOからメール。2023-5-30に指摘された箇所を修正したので、再度原稿をチェックし48時間以内に返送せよと。校正原稿を見ると、ちゃんとYahioがYashioになっている。「大丈夫です」と返信。これでアキレス腱付着部症の最小侵襲手術のレビュー論文も近日中にpublishされそうだ。
2023-6-11:FASの査読。どうしてディスカッションで、自分たちの研究結果とは直接関係のない論文をダラダラと引用するのだろう。自分たちの研究結果をまじめにとらえていないというか、水増しというか、こういうディスカッションを読むと吐き気がする。研究結果にフォーカスした論文の引用とこの研究結果との比較をするよう指摘。終わったので提出。
2023-6-12:IFFAS 2024の発表原稿の準備。英語論文を朗読したら、1文1文が長くて聴くに堪えない。そこで、さっそく発表用原稿を作ってしまい、それを朗読することに。まずは英語論文の手術法の部分を1文1文読みながら細切れにする作業。
昨日査読が終わったFASの出版社SAGEからお礼のメール。お礼として、SAGEのジャーナルを60日間無料閲覧できるようにしますと。これはラッキー。重度外反母趾の論文で引用しようと思っている文献の中にFoot & Ankle International(これもSAGEのジャーナル)の文献があったが、まだ新しいために入手できていなかった。早速これをダウンロード。ついでに、自分のアキレス腱付着部症の内視鏡論文を引用してくれていた論文があったので、これもダウンロードしてみた。見ると、ハグルンド変形とアキレス腱付着部症のレントゲンという、まさに今EJR Openに出している自分の論文とかぶる内容。
2023-6-13:英語の原稿を作るより先に発表のパワーポイントを作り、それに発表原稿を載せた方が早いと思い、早速パワーポイントづくり。以前足の外科学会で発表したパワーポイントを英語にすればいいので楽。後は最近論文に書いた内容や動画などを加えればよさそう。英語の勉強としては、仕事以外の時間はずっと英語で過ごそうと思い、インターネットの設定をすべて英語に、YouTubeの言語設定も英語にした上で、過去の日本語動画の履歴をすべて消し、足の外科やパソコンの用語で検索した動画だけで満たすようにした。
2023-6-14:昔少し英会話教室に通っていた時、教室に行く直前、英文法の例文集を朗読してから行ったらすらすらしゃべれた経験から、英文法を中心とした英語音声教材が会話に有効のような気がして、いくつかAmazonで購入。こういう学習教材については昔からあまり吟味してから買うつもりはなく、いくつか買って相性の合うものを使うようにしている。数日後に届く予定。また、英会話の本を買うのなら、日本人向けに書かれている教材よりも、英語で書かれている本を買った方がよいに決まっているから、Amazonで”English conversation”で検索して出てきたものの一つ “English Conversation: Comprehensive Study Program (Practice Makes Perfect)” をKindleで購入。早速見てみると、数百語の短い会話文があり、その中で汎用性のあるフレーズが太字となっていて、そのフレーズの解説が後に続いている。汎用性のあるフレーズの多くは、会話文特有の「つなぎ」とか「冗長」とか「あいまい」とか「同意」とか「感嘆」などのフレーズに焦点がおかれている。確かに、話しているときは、そういうつなぎの言葉で時間稼ぎをして、次に何を話すか考えながら話している気がする。英語だとそういう言葉を知らないから、いきなり完全な文を話さなければならないプレッシャーにかられるのかもしれない。
続いて、昔買ったものの読まなかった「国際学会English スピーキング・エクササイズ口演・発表・応答」を最初から読みはじめてみた。発表の最初には「フレームワークを話せ」とのこと。まぁ当然。載っていたuseful phrasesを用いて、最初のスライドの発表原稿を作成。
2023-6-15:IFFASの発表スライドと発表原稿の作成。
昨日買ってよかったPractice Makes Perfectシリーズには他にも多くの本が出版されているので、それを見たところ、英文法の本もいくつか出ていた。2000円程度だし、Kindle本でかさばらないので、つい3冊も衝動買い(Practice Makes Perfect: English Grammar/Intermediate English Grammar/Advanced English Grammar for ESL Learners)(だんだん難しくなるという3部構成ではなく、3部に分けて英文法全体を解説)。英文法といった小難しい規則をこういう簡単な英語で説明していることに感動。その中でも、使役の意味を持つ他動詞を、英語の歴史を簡単に振り返りながら説明していたのには感動した。自分の場合、英会話本で、自分が決して遭遇しないような会話場面で練習をするのは好きでなく、このような英文法の本で、構造を意識しながら文を組み立てる練習をするほうが合っている。
2023-6-16:IFFASでの質疑応答で質問されそうなことをメモ書き。ちょっと考えただけでもすぐに30個くらい質問が思い浮かんだ。これらの答えを用意しておき、これに似た質問のときには強引に用意した答えを言えばいいだろう。用意した答えに結びつけるためには、答えを限定したり、一般論にしたり、ここでは答えられないと拒否したり、別の質問に置き換えたり…などのつなぎのフレーズも用意しておく必要がありそうだ。
2023-6-20:WJOのサイトに行き、自分の論文がpublishされているかどうか見たら、一昨日publishされていたよう(こちら)。とりあえずめでたい。
2023-6-22:IFFASのための英語の勉強。
添削された英文を朗読するとよいと聞いたことがあるので、今まで書いた論文を、文献番号などを取り除いて朗読しやすくしたものを作成。久しぶりに読んだら、書いたことを忘れかけているので、思い出すのにちょうどよい。Wordに付属する音読機能で聴いてみると、長すぎて集中力が続かないので、これは役立たなさそう。Abstractだけを音読さんでMP3ファイルにして、それだけ聴いたほうが、集中力が保てるので良かった。
続いて、この前買ったPractice Makes PerfectのEnglish Grammerのある章の例文を全部書き出してみると、同じような文法事項の例文が並ぶので、これは朗読・リスニングにも使えそう。ひとまず全部書き出して音読さんで音声ファイルにしてみよう。
同じくこの前買った英文法書についていたCDは、区切りを示す”Chapter 1, page 1”のような言葉が煩わしいし、途中のエクササイズで中途半端な文になっているものがあったりして、聴く気にならないので断念。そういえば昔ヒアリングマラソンを1年間買って、そのCDがたくさん家にあるのを思い出して聴いてみたが、これがおそろしくつまらないので、これも断念。やはり楽しい方が良いので、YouTubeでリスニングに役立ちそうなものの探索。Interviewで調べて出てきたネイティブのTalkチャンネルのものを聴いたが、つなぎの言葉が多いばかりで、大した内容のない会話をしているものも多かった。これは、相手の意味のない言葉の中から意味ある内容を拾い出す練習にはいいだろう。むしろ、スピーチを集めたチャンネルや、映画から会話部分を切り取って、それに解説を付けている英語教育チャンネルなどのほうが役立ちそうだった。さらに、非ネイティブ向けのEnglish conversationチャンネルも使えそうだった。
あとは日々の練習として、会話のトピックスごとに、自分の言いたいことを英作文してまとめていくのもよいか。とりあえずはこのあたりを続けてみよう。
2023-6-24:英語の勉強のことを考えだしてから、途端日々の気分が悪くなった。なぜかと考えてみると、どうやら英語の勉強は成果が見えにくいからのよう。成果の見えない努力をしていると、その日その日が意味あるものに思えなくなっていくのである。若い時の努力ではそんなことを気にしたこともなかったが、年を取ってくると、「いつまで生きているのかわからないのに、そんな成果の見えない努力に時間を使えるものか!」などと思ってしまう。
しかし、来年の国際学会に向けて、英語の勉強もやらなければならない。では、成果の見える英語力の向上とは何だろう。それは、話せなかったことが話せるようになり、聞き取れなかったことが聞き取れるようになることだろう。「話す」とは自分から発せられるものなのだから、何を言うかは自分次第である。それならば、「自然に話せるようになる」などといった曖昧なことを目標とするのはなく(そもそもそんな目標は到達できるのか?)、「話したいことをまとめる」という成果が見える形の努力にしたほうがいいだろう。一方、「聞き取れなかったことが聞き取れるようになる」にはどうすればいいのだろう。それは「同じものを何度も聴く」ことによって達成されそうだ。例えば、一発では聞き取れないレベルのYouTubeの動画を一日一本何度も繰り返し聴き、そこで話している内容を理解し、空で追唱できるレベルにまで引き上げれば、「目に見える成果」を出せたと言えそうだ。
2023-6-25:今日もIFFASまでの英語の勉強法の模索。とにかく目標に向いていない英語の勉強をしたくない。そう考えると、YouTubeすら見たくない。ひとまずは自分の英語論文をWordのイマーシブリーダーで音読させたものを聴くのが一番落ち着く。また、Mann’s Surgery of the Foot and Ankleを朗読するのも悪くなかった。久しぶりに自分の最初の論文””Arthroscopy of the First Metatarsophalangeal Joint”を聴いたら面白かった。今では到底かけないような尖ったことを書いている。このくらい毒があったほうが、読んでいる方は楽しいだろう。
2023-6-27:英語の努力に関しては、IFFAS英語日記に移行することにした。理由は、論文日記は論文のモチベーションのために書いているので、かけ離れた内容を論文日記に書いて何となく論文をやった気になりたくないのと、英語の勉強はひとつの日記として独立したものにしたほうが、後から見て参考になるだろうと思ったから。ということで、今後の英語の勉強についてはIFFAS英語日記に移行します。
2023-8-19:2023-6-7にメールが来たハーバード大学に留学中の北京大学の先生からまたメール。推薦状が出来上がりましたのでサインを下さいと。しばらく連絡がなかったから、何人か推薦者の候補にメールを出し、返事が来た人の中から最適な人を選ぶという方法を取って、こちらはお役御免になったかなと思っていたが、弁護士さんと相談しながら推薦状を作っていたので時間がかかりましたと。とりあえずそちらはただサインして返送すればいいのだが、それに加えてこちらの履歴書も送ってくれませんかと(これもUS immigrant officeから要求されるとのこと)。まぁ別に送るのは構わないが、振り返ってみればあまりに華のない履歴書で、逆にマイナスポイントにならないか(笑)
2023-8-20:推薦状の内容にはあまり興味がなかったので、ただサインだけして返送してしまったが、あらためてその推薦状を読んでみると、推薦者としてのこちらの簡単な自己紹介として「私は八潮中央総合病院整形外科の足の外科センター長であり…」とか「2003年東大医学部を卒業し…」などと書かれてある。おそらくORCIDという世界の研究者に割り振られたIDでこちらの色々な情報を入手して書いたようだ。なんと綿密な!足の外科センター長というのは、去年、そろそろ色々な本に執筆する機会などが増えてきて、その際、自分の名前が他の執筆者の大学准教授やら講師やらの中に並んだとき、センター長くらいの役職についていないと浮くので困る、という理由で、無理やり病院に役職名の振り当てをお願いしたものだ。これも今回の推薦者として少し役立ったかもしれない。また、東大医学部卒業でよかったと初めて思った(笑)
その北京大学の先生から返信メール。大変ありがとうございますと。また、履歴書を作る負担を少しでも減らすべく、テンプレートを作りましたので、そちらに記入してください、もし日本語での履歴書があれば、翻訳も含めてこちらでします、などと書かれてあった。その熱量がすごい。また、推薦状の自筆サインが漢字だったのに親近感がわいたのか、今回のメールでは、その先生の名前の英語読みの後に漢字が書いてあった。
2023-9-3:ここ1,2週ばたばたしていたので、履歴書の作成もpendingにしてしまっていたが、そろそろ送らないと相手方に失礼だ。ということで、ここ数日間、履歴書を英語にしているが、これがとてもめんどくさい。自分が専門医になった日とか難病指定医に指定された日などもいちいち調べなければならないし、特にめんどくさいのが学会発表の履歴だ。学会発表など旅行の口実のためにしているだけであって、終わったらそのままなくなってしまうものくらいに思っていたが、今回の履歴書ではそれも書かなければならないので、昔の資料などを調べてまとめている。いい加減にして出したい気持ちにかられるが、お粗末な履歴書だと推薦人としてマイナス査定されて相手に迷惑がかかるので、枯れ木も山の賑わいとばかりに、キャリア上の履歴と呼べるものは全部書かざるを得ない。
2023-9-4:北京大学の先生に履歴書の送信。とても丁重な英語のメールに対する返事が小学生のような英語のメールで申し訳ない限りだが、これは英語力の差なのでしかたがない。とりあえず義務は果たした。
2023-9-6:北京大学の先生からお礼のメール。それにしても丁重な文章がうまい。全文載せたいところだがそうもいかないので、締めくくりの言葉だけ載せると ”I believe our paths will cross again in the future. Until then, please accept my heartfelt appreciation for everything you’ve done. Thank you so much, Dr. Nakajima.” と書いてあった。上手い。こちらからの英語のメールの中に前回知ったあちらの漢字名と自分の漢字名を書いたが、あちらからのメールにもそれが書いてあった。英文の中にお互いの漢字名が書いてあると、英語を主戦場とする同志という感じで親近感がわく。彼の名前を知ったので、彼の今後の活躍をPubMedで見たいと思う。それは向こうからも言えることだ。またがんばろう。